第2話 – それでも夜は明ける
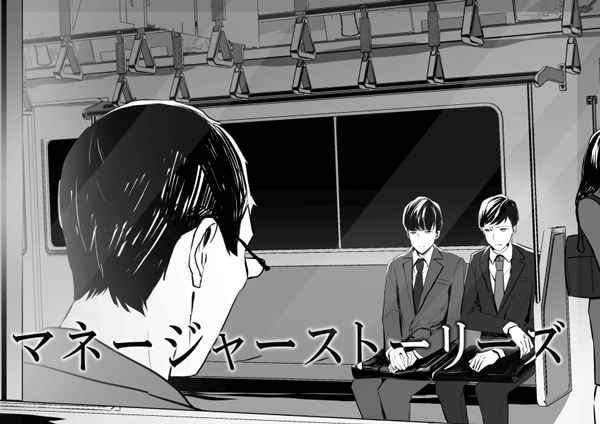
自立しているものこそ、お互いに接触し頼るべき時は頼って生きているが、
十分に自立していない人間は、他人に頼ったり、交際したりするのを怖がる。
河合隼雄
「働きざかりの心理学」より
前章までのあらすじ
株式会社ワークカラット企画部マネージャー、横井一茂は、売り上げ低迷の打開策となる新企画を、部下の伊藤・田中と共に作っていた。
しかし企画会議当日、同期の井田による指摘に答えられず、手応えは感じられない結果に終わる。
その夜、横井は恋人の純と口論になり、純は泣き出してしまう。
1
目が覚めると、隣に純はいなかった。

横井の恋人。文房具会社に勤めており、サバサバとした性格ながらも人望は厚く、仕事も速いキャリアウーマン。しかし家(横井の前)ではそのスイッチが切れ、片付けも疎かにするなど、ズボラな一面も見せる。
昨夜のやり取りもあり、顔を合わせ辛かったのだろう。僕は髭を剃りながらそんなことを考えた。
いつも通り家を出て、一駅分を会社まで歩く。
歩道に人は少なく、僕の数メートル先を母親と、まだ五歳くらいの男の子が歩いていた。
男の子は赤い帽子を被り、不機嫌そうに足を引きずりながら歩いている。母親の方は男の子の手を引き歩き出そうとするのだが、男の子はときどき立ち止まっては母親に抗っていた。
「もう、しょうがないなあ」
2人を追い越した後に母親の声が聞こえ、振り返ると、男の子を抱きかかえようとしているところだった。横顔しか見えないが、一つ結びにした髪型と雰囲気が、どことなく純に似ている気がした。
── 今だってカズはどうせ、昨日今日、私が急に機嫌が悪くなったくらいにしか思っていないんだろうけど、そんなんで、私たちこの先うまくいくと思う?
男の子の笑い声を聴きながら、ふいに、昨夜純に言われたセリフを思い出す。
今まであんなに大きな喧嘩をしたことなどなかった。もちろん小さな不満はあっただろうけど、あそこまで純の感情を高ぶらせてしまうようなものはどこにも思い至らなかった。
再び僕は歩き出し、信号待ちの交差点で、「朝会えなかったので、心配しています。今夜ゆっくり話そう」というメッセージを、純に送った。
2
デスクの上に鞄を置くと同時に、伊藤が「横井さん」と声を掛けて近寄ってきた。

「メディア企画開発部一課」マネージャー。
この春に昇格したばかりで、自身もこれまでの業務とのギャップに戸惑いつつも、新規企画立ち上げに向けて部下たちと協力し、奔走している。
「人の気持ちを察することに長けている」とは本人の談。年下の恋人・純との結婚も考え始めている。
「田中君から、今日は休ませてほしいって連絡がありました」

伊藤の同期で、同じくアシスタントディレクター。自分の意見を発信するのが苦手で、大勢の会議の場となると沈黙することがほとんど。大の映画好き。
「どうして? 具合でも悪いのか」
「はい、頭が痛くて調子が悪いらしくて。確かにつらそうな声でした」
「そうか……わかった。ありがとう」
僕が笑みをつくると、伊藤もつられて笑顔を見せ、自分の席に戻っていった。
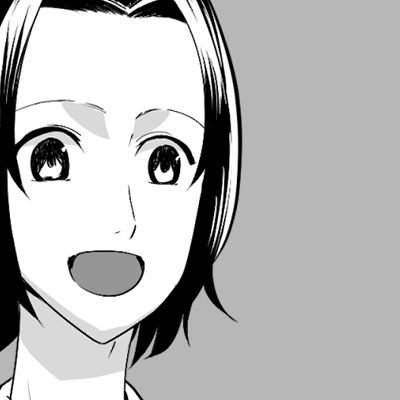
「メディア企画開発部一課」アシスタントディレクター。横井の部下。横井を慕っている。自称「猪突猛進型」で、考えるよりまず先に行動する。喜怒哀楽の表現が豊かで、それが長所でもあり、時には短所にもなると横井は考えている。
田中は昨日も頑張っていたし、今までも連日残業続きだった。緊張の糸が切れて、疲れが出たのかもしれない。疲労熱なら、明日には回復するだろう。僕はそんなことを考えながら、メーラーを立ち上げてチェック作業に入っていく。
小一時間ほど作業をし、ある程度のメールに返信をしたところで顔を上げた。伊藤と一瞬だけ目が合ったが、すぐに反らされた。昨日のプレゼン会議の一件から、もしかしたら色々思い悩んでいるのかもしれない。何か話しかけてみようと思ったが、PCを見つめる彼女の眉間に小さくしわが寄せられているのを見て、それを辞めた。
昼休み後すぐに行われたサイトのリニューアルの打ち合わせでは、小さなミスをいくつかした。配布しようと用意していた資料を忘れて取りに戻ったり、前回の打ち合わせで結論がでていた点を再び指摘してしまったり。
予想より長引いた打ち合わせを終えて、席に戻りスマホを手に取った。純からのメッセージがないことを確認すると、思わずため息をついた。それから、昨日のプレゼン会議で使用した資料を手にし、再び読み返してみる。
昨日までは「良くできた企画だ」と思っていた。でも改めて今見ると、少しずつ粗も見えてくる。「皆の関心を惹く」という点では良く作りこまれている。でも、「この企画で、会社の未来を切り開いていく」と言うには、やや表面的な内容でしかなかった。井田の言う通り、考え抜かれた企画書ではないように思えた。──一日を経て、こうも違う印象を抱くとは。
「横井さん」と伊藤が声をかけてきた。顔を上げると、心配そうに僕のことを見ている。
「企画案、どこか手直しの指示があったんですか。私も手伝いますけど」
僕がずっと資料を見ているので、そう思ったのだろう。
「いや、結果がでるのは明日。それまでに、もう一度見直しておこうと思って」
「そうですか」
伊藤の表情は少し暗かった。彼女も、僕と同じようなことを考えていたのかもしれない。
「すみません、力不足で」
「そんなことないよ。俺がもう少し対策を練っておくべきだった。井田、結構細かいところを突いてきたしね」

「メディア企画開発部一課」ディレクター。横井の同期。先に昇進した横井にライバル心を抱いている。同僚からの信頼も厚いが、会議などの場においての有無を言わせない的確な指摘に、周囲は恐れを抱いてもいる。
思わず愚痴めいたことを言ってしまう。その場を離れたくなって、僕はおもむろに立ち上がった。
「ちょっと、息抜きしてくる。すぐ戻るから」そう言うと、僕は部屋を出た。
喫煙室には、片桐さんがいた。
「メディア企画開発部一課」ディレクター兼クリエイター。エキスパート職であり、横井にとっての年上の部下。のほほんとした佇まいで人望も厚いが、時折、的確なアドバイスを投げてくる。ヘビースモーカー。
「やあ、昨日はお疲れ」
片桐さんは煙を吐き出しながら、のんびりとした声を出した。
「どうも、色々とありがとうございました」
「いやいや、仕事だしね」
僕は片桐さんの隣に立ち、煙草を取り出した。そして、少し間をおいてから「昨日のプレゼンの件、もう部長に報告されたんですか」と尋ねた。
「うん。まあでもその話は、部長から直接ね」片桐さんはニコリと笑って、それから、
「良い経験していると思うよ、横井くんは。大変だろうけど、きっと未来の糧になる」
と付け加えた。──まだ希望があることを言っているのか、それとも、失敗から学んで、一から出直せということなのか、今一つ真意が分からない言葉だった。でも、片桐さんはそれ以上何も言ってこなかった。
「片桐さんも大変な経験、たくさんしてきたんですか?」
「もちろん」と、片桐さんが頷く。「あれは小学生の頃だったかな」
「いや、子供の頃の話はいいですよ」
僕は少しだけ可笑しくなってそう言った。この人は、いつもそうやって話をはぐらかしながらも、場を和ませてくれる。
「もっと最近になってからのやつでお願いします」
「最近ねえ……」
片桐さんはしばらく悩んでいたが、しばらくして「思い出せないや」と言った。
「嫌なことはすぐ忘れるタチだからね」
「皆が片桐さんみたいに考えられたら、世界はもっと平和になるでしょうね」
「でも不思議なもんでさ、子供の頃の嫌な記憶って、今思い返してみるとあれはあれで良かったって思うじゃん。あれ何でだろうね」
片桐さんは僕の皮肉などお構いなしに、二本目の煙草に火をつけながら話し出す。
「俺は思うんだけどさ、
よく、『過去は変えられない』って言うじゃない? けどそれって本当かなって思うんだよね。あれはあれで良い思い出だったって思ったらさ、当時の出来事も良かったものに塗り替えられていく気がするんだよ。
今の自分が、過去の自分に影響を及ぼすことだって、俺はあると思うんだよね」
「はあ」
正直、何を言っているのかよく分からなかった。
片桐さんはふと時計を見上げ、「あっ」と声を出した。
「いかん、会議の時間だ。──どうも横井くんと話していると、時間にルーズになっちゃうな」
「…いやいや、話してたの殆ど片桐さんじゃないですか」
「そうだっけ?まあいいや、そろそろ行かないと。それじゃあね」
片桐さんがいなくなった後、僕はひとり喫煙所に残って二本目の煙草に火をつけた。
──本当に過去を変えることができたら。プレゼン会議や昨晩の純とのやりとりを、違った結果に塗り替えていくことはできるのだろうか。
多分、片桐さんの言っていることはそういうことではないのだろう。でも、そのことについて深く考える気にはなれなかった。僕にとって、それらの過去と今は地続きだった。それらは「過去」で完結せずに「現在」も継続している問題なのだ。そして僕は今、どちらの問題に対しても待つことしかできなかった。プレゼン会議の結果についても、純からの返信も。
結局、席に戻ってからも仕事に身が入らず、どうにも中途半端な一日だった。どうしても、プロジェクトの行く末と純のことが頭に浮かび、集中できない。こんな日は早く帰るに限る。
就業時間を30分ほど過ぎた頃、帰り支度を始めた。そんな僕の姿を認めて、PCに向かっていた伊藤が「もう、お帰りですか」と声を掛けてきた。
「うん。会議の結果が分からないことには、動きようがないからね。伊藤さんも早めに帰った方がいいよ。このところ遅い日が続いてたし」
「ありがとうございます。私もそろそろ帰ります」
伊藤はわずかにほほ笑んだ後、少し声を落とした。「田中君から連絡はありましたか」
「いや。明日は大丈夫なのかな」
「まったく、どういうつもりなんでしょうね」
伊藤は少し苛立ったように言った。
「企画の結果が気にならないのかな。明日は出て来られるかどうかくらい、連絡してくればいいのに。そう思いません?」
「まあ、疲れが出たんだろう。このところ、プロジェクトにかかりっきりだったし、会議でも緊張しただろうし」
そういうと、僕は鞄を手にした。「じゃあ、今日は早めに帰るよ。お先に」
席を離れると、伊藤が「お疲れさまでした」と言った。
家までの道をを歩いていると、純からメールが届いた。タイトルには『自分の部屋に戻ることにしました』という文字があった。
「は?」
僕は思わず声に出してしまった。慌てて周囲を見回したが、幸い近くに人はいなかった。
僕と一緒に暮らすようになる前、純は横浜の賃貸マンションで一人暮らしをしていた。僕が中野坂上のマンションに引っ越す際に「一緒に住まないか」と誘ったのだった。
前のマンションを解約したらどうかと何度か話したが、彼女はその度に曖昧な返事でそれを流していた。
僕は急いでメールの中身を確認した。
『色々考えましたが、しばらくは私たち別々に過ごした方が良いと思います。
今日明日と、会社は午後休を取っていますので、その間に荷物を片付けます。』
何度か読み返すうちに苛立ちが増していった。
なんでそう勝手に進めるんだ?こっちの気も知らないで。
確かに最近の僕は仕事にかまけて見えたかもしれない。だけどそれはマネージャーになったからだし、課の花形ともいえるプロジェクトのリーダーに選ばれたからだ。それ以来、僕がどれだけこのプロジェクトに力を入れているのか、純にだって話はしてきたというのに。
帰宅してからも、僕の気分を苛立たせる出来事が待っていた。
「これ見よがしだよな……」
リビングに純の姿はなく、代わりに折り畳まれた段ボールがいくつも壁に立てかけられていた。
「勝手にしろよ」
目の前の段ボールに向かって、僕は思わずそう吐き捨てた。
3
次の日も田中は出社していなかった。しかも、今日は連絡なしだ。
伊藤が田中の携帯にかけてみたが、すぐに留守電になったという。メッセージも送ってみたが、返事は無い。
「連絡もできないような状況なのだろうか」という心配もちらりと浮かんだが、「昨日休んでしまったことが気まずく、なかなか連絡できないだけだろう」と考えた方が自然な気がした。田中なら、そんなこともあるような気がする。大事にすると、かえって逆効果かもしれない。
昼休み、純に電話をかけてみた。しかし、すぐに留守番電話のメッセージが流れた。
田中の電話にもかけてみたが、やはり、留守番電話のメッセージが流れる。「横井です。心配しているので、一度、連絡をください」そう短く伝言を入れると、大きくため息をついた。
野津部長から内線がかかってきたのは、14時10分前だった。
「今、大丈夫か」
そう一言だけ尋ねられた。「はい、大丈夫です」と答えると、部長は「じゃあ、俺の席に来てくれ」と言った。要件は恐らく、プレゼン会議の結果についてだろう。
野津部長の席は僕の席から少し離れたところにあり、席の横には小さな応接机とソファが置かれ、周りをつい立てで囲っている。「失礼します」とつい立ての中をのぞくと、部長は席に座って難しい顔をしていた。
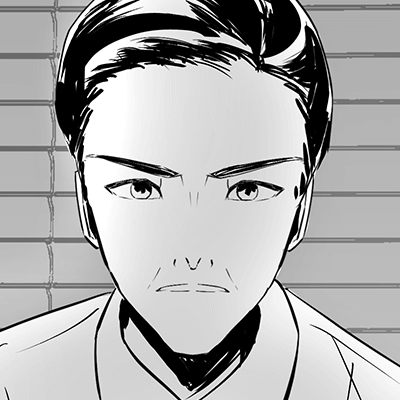
「メディア企画開発部一課」部長。
ウィットに富んだ冗談を言い、しかるべき場所では冷静な一面も見せる、横井から見る「理想の上司」。
学生時代にラグビーをたしなんでおり、今でも体系は維持している。
部長は僕の顔を見ると、日焼けした顔を光らせながら「おっ」と声を上げ、少しだけ表情を緩ませてから「そこに座れ」と、ソファの方に腕を伸ばした。
半袖のシャツから太い上腕筋が見えた。学生時代にラグビーをやっていたというその体格は、現在もその面影を感じさせる。部下思いでウィットの利いた冗談も言い、しかるべきところで厳しさも見せる、理想の上司だ。だが今は、その威圧感からか、それともこれからの時間を想像してか、部長の存在に息苦しさを感じた。
「これまで、進めてもらったプロジェクトのことだが」
部長は前振りもなく、口を開いた。
「リーダーは井田に引き継いでもらおうと思う」
(──そう来たか)と、心の中でつぶやいた。不思議と、予想していたほどのショックは無い。
「お前は、引き続きチームの会議には参加しろ。ただし、後方支援だ。プロジェクトのプランニングは、井田の方でまとめてもらう」
「わかりました。ですが、そう決断された理由もお話しいただけませんか」
僕が尋ねると、部長は組んだ指元を見つめ、短く息を吐いた。
「企画書の内容を見させてもらったが、あれは言うなれば、『横井一茂のレポート』だな。お前の想いや考えが余すところなく込められているように感じたよ。でも、それだけだ。それ以外、何も見えてこなかった」
「つまり、私の出した企画の品質が良くないかったということですか」
「俺がお前に期待したのは、チームと課のメンバーを巻き込んで新プロジェクトを成功させることだ。お前の個人的なアイデアを見たかったわけじゃない」
「分かっています。だからこそ、良い企画にしていこうと、私なりに尽力してきました。この数週間、本当にプロジェクトのことだけ考えていました」
「ああ、知ってるよ。でもそれは、マネージャーの働き方じゃないんだよ」
追い打ちをかけるように、部長はそう言った。
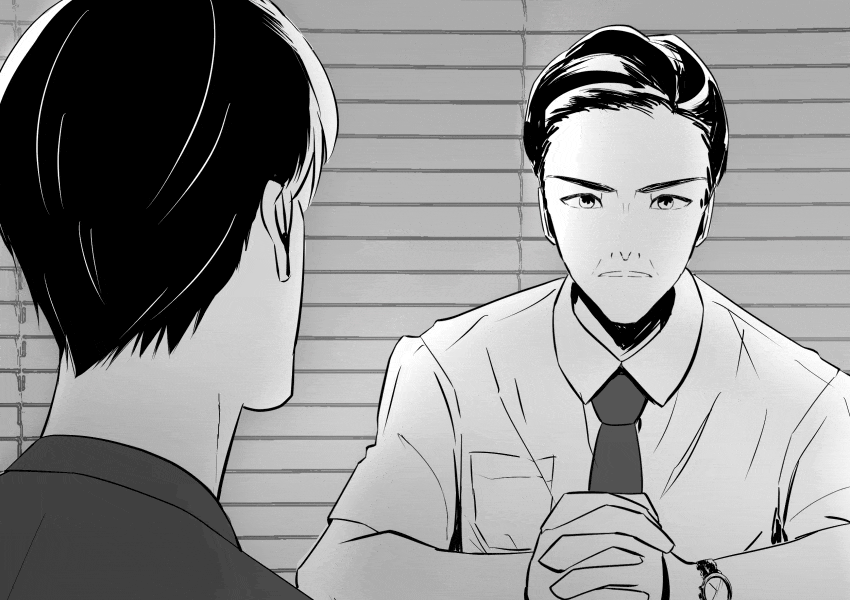
「野津部長の言うマネージャーの働き方とは、なんですか」
「まず、自分で考えろ。今後の進め方については、追ってメールする。それまでお前は、井田への引継ぎの準備をしておけ」
部長はそう言って、ソファから立ち上がった。慰めもねぎらいの言葉もなかった。僕も無言で立ち上がり、部長の方を見ずに自分の席へと向かった。
席に戻ると、伊藤が心配そうな目を向けた。「プロジェクトのことですか」遠慮がちに伊藤が尋ねた。
「うん」僕は何をどう話したらよいのか、わからなかった。まだ、部長の言葉が頭に残っていて混乱していた。「どうでした」と伊藤は続けて尋ねた。
伊藤は真剣な眼差しで僕の瞳を見据えていた。なにもかも読み取られてしまうような気がして、僕は目を反らした。
「さらに内容を検討して、ブラッシュアップしてほしい、って」
リーダーを降ろされることは言わなかった。
「本当ですか!ボツじゃないんですね、よかったあ」
伊藤は声のトーンを高くして、嬉しそうに言った。
確かにそうだ。僕は思った。ボツにならなかったのだから、まだ失敗したわけではない。僕はともかく、伊藤と田中にとっては、まだチャンスが残っている。それは喜ぶべきなのだろう。
「そうだな。引き続き、頑張ってくれ」
おそらく、伊藤と田中は、井田の元で続けることになるだろう。なんの根拠もなく、僕はそう思った。
「どの辺を指摘されたんですか。私、さっそく検討しますよ」
すっかりやる気を取り戻した伊藤は、ぐいと身を乗り出してきた。
「いや、その辺りは、また改めて打ち合わせすることになっているから。この件は少し待ってくれないか」
そう言って、僕は立ったままだったのに気付き、椅子に腰を下ろした。伊藤も何かを察したのか「わかりました」と少し声を低くして言うと、自分の席に戻り、キーボードを叩き始めた。
当面の課題を失った僕は、その日も定時過ぎに会社を出た。マンションに戻ると、ダイニングテーブルの上にメモ書きがあった。
『必要な荷物は持ち帰りました。残りはまた日を置いて取りに来ます』
整った純の字を見ていると、初めて会った日のことを思い出した。あの日も、純はすらすらときれいな字を、僕の前で書いて見せた。
僕は椅子に座ったまま、台所をぐるりと見まわした。昨日までは純に対する苛立ちの方が勝っていたが、彼女の荷物が減りつつあるこの部屋の現状を目にすると、不思議と苛立ちは霧散し、反対に焦りばかりが胸を占めていく。
部屋の中が少しすっきりし始めたことにより、角に置かれた観葉植物が、よりその存在感を醸していた。
モンステラの花言葉って知ってる?と、ある時純が聞いてきたことがある。
当然、僕は知らなかったし、まだ膝丈ほどの大きさだったその植物の名前も、そこで初めて知ったくらいだ。
「『献身』っていう意味なんだって」
「ケンシン?」
彼女は買ってきたばかりのモンステラをどこに置こうか迷っているようで、両腕に鉢を抱えたまま部屋の中を行ったり来たりしていた。
「持つよ。重いでしょ?」
純から鉢を受け取ったが、思っていたよりは重くなかった。
小さな鉢を抱える僕を見て、純は小さく笑った。
「なに?」
「いや、似合わないな、と思って。そういうの」
「花を持って様になったら、それはそれで複雑な気持ちだけどね」
「ううん、そういう意味じゃなくて」彼女は続きを言いかけて止まり、窓の外を眺め再び話し出した。
「モンステラってね、今は想像できないかもしれないけど、すごく大きくなるの。葉っぱなんてもうこんなくらい」
純が両腕を目一杯横に広げるジェスチャーをした。
「嘘だ、そんなわけないだろ?」
「本当だってば。そのうち分かるよ」
純は「ここに置いて」と、本棚の脇を指さす。言われた通りの場所に鉢を置き、彼女と並んで、少し後ろから眺めてみる。
水をやり忘れたりなんかしたら、あっという間に枯れてしまいそうなほど、根元は細く、小さな葉を頼りなく左右にぶら下げている。
本棚の横に控えめに佇むモンステラからは、純の言うような急成長の気配は微塵も感じられなかった。
そのとき僕はようやく、「ケンシン=献身」という字面が、頭の中に浮かんだ。
彼女の言う通り、あれから見る見るうちにモンステラは大きくなった。反対に、僕たちの会話は減っていったように思う。モンステラはまるで僕たちの間の沈黙を吸い取り、成長したようにも思えた。
彼女からは昨日のメール以外、連絡がない。昨晩からの苛立ちはやがて焦りに変わり、今はただ悲しみだけが募っていた。
片桐さんの言うように、今のこの辛い心情もいつか過去となり、「そういえばそんなこともあった」と笑ってやり過ごせるようになる日が来るのだろうか。そしてその時、僕の隣に純は変わらずいるのだろうか。目の前で幅を利かせるモンステラに無言で問いかけたが、もちろん植物は答えてなどくれない。
4
次の日も田中は会社を休んだ。事前に連絡はなく、2日連続の無断欠勤だった。伊藤に連絡があった初日を入れると3日連続の欠勤。「そろそろ、放ってはおけないな」と僕は思った。
伊藤は「何度かけても繋がらないんです」と申し訳なさそうに言った。もちろん、僕もかけてみたが、すぐに留守電のメッセージに切り替わった。
「どうしちゃったんだろう」
伊藤は本当に心配そうだった。最悪の事態を想像しているのかもしれない。「私、家に行って見てきましょうか」とも言った。
伊藤の真剣な顔を見ていると、僕もなんだか心配になってきた。確かに、風邪にしては3日は長いかもしれない。
「俺が今日行ってみるよ」
僕がそう言うと、伊藤はホッとした表情を見せた。
「私も行きますよ」
「いや、いいよ。俺が1人で行くよ。俺の仕事だから」
「でも、私も田中君のことが気になります」
「うーん、2人で行くと、田中もかえって気にするかもしれないし。俺が行ってくるよ」
そう言うと、伊藤はようやく引き下がった。
「じゃあ、お願いします。私も心配してたって言っておいてくださいね」伊藤は軽く頭を下げて、席に戻った。
伊藤とのやり取りを終えると、PCの電源を入れた。今日中に、井田への引継ぎ資料を作り終えようと決めていた。
資料作りは思ったよりサクサクと進み、それ以外の急ぎの仕事もなく、僕は田中の家に向かうため、17時過ぎに会社を出た。
田中は西荻窪に住んでいる。西荻窪までは、西新宿から荻窪まで向かい、そこからJR線に乗り換える。駅のホームにはすでに帰宅中のサラリーマンがちらほらいた。電車はそれ程混んでいなかったが、空いている席はなかった。
西荻窪駅に着き、商店街を抜けて住宅街に入り、そこから更に数分歩いた先に白い壁に青いレンガ屋根の古びたマンションが見えた。
インターフォンを押してみるが、返事がない。まさか中で倒れているんじゃないかと心配になり、続けて数回インターフォンを鳴らした。すると、玄関の向こうで微かだが物音がしたのがわかった。
『……はい』
スピーカー越しに聞こえるのは田中の声だ。僕はわざと明るい声でスピーカーに向かって声をかけた。
「横井だ。急にすまん。連絡が取れなかったから様子を見に来たんだけど、大丈夫か?」
『え、あ、はいっ』
慌てたような声が聞こえたところでスピーカーが切れた。すぐに玄関のドアが開かれる。
しばらくして部屋から出てきた田中は、ひどく憔悴した様子だった。
よれよれの部屋着、ぐしゃぐしゃの髪の毛、髭も伸びたままだ。とてもじゃないが、外に出られる格好じゃない。休んでいる間、ずっと部屋に籠っていただろうことを容易に想像させる姿だ。
「ごめん、驚いたよな急に押しかけて。あ、でも、田中も悪いんだぞ? 連絡しないから、みんな心配してるぞ」
僕は冗談めかしたように笑った。まるで演劇の書き割りのように白々しいセリフに、自分でも呆れた。
「なあ、ちょっとだけ話できないかな。腹減ってない? 場所変えようか、って言っても 俺あんまり西荻とか来たことないからな――」
「横井さん」
ほとんど掠れそうな声で田中が呼んだ。
「どうした?」
「隣の方の迷惑になるので、あんまり大声では、」
「あっ……そうだよな。悪い……今日のところは俺、帰った方がいいかな」
田中は思いつめた様子で自分の足元を見ている。何か言いたいことがあるのかもしれない。僕は辛抱強く待つことにした。
「……すみません、あまりお腹は減ってなくて。外に出るのも今はちょっと」
「分かった」
「でも、僕も、横井さんと話はしたいと思っています。なので……もしよければ入りますか?」
田中が後方を指した。
「……中に入ってもいいの?」
どうぞ、と田中が言い、僕が入れるように脇へ退いた。
外観は古ぼけているが、部屋の中は比較的新しいように感じた。壁紙は白く、シミ一つない。リビングに入ってすぐ、目の前の壁に『ゴーストバスターズ』のポスターが貼られてあるのが目に入った。
部屋の広さはせいぜい六畳半といったところだが、家具が少ないため広く感じる。テレビや本棚、ソファ、冷蔵庫といった必要最低限のもの以外に何もないところは、会社での田中のイメージのままであるように感じた。
小さな卓袱台を挟んで僕たちは向き合った。僕がソファに座り、田中がフローリングの床に座る。
何から話すべきか、分からなかった。この前のプレゼン会議での失敗へのフォローなのか、それとも僕がチームリーダーを外されたことなのか。田中も「話したいことがある」と言いながら、いつものようにうつむいてしまっている。壁にかけられた時計の針の音が、いやに大きく聴こえた。
「なあ、あの棚のって、全部DVD?」
僕は、本棚にぎっしりと並べられたパッケージを見ながら、田中にそう尋ねた。
「いえ。二割くらいはサントラCDとかですね」
整然と仕舞われているそれは、何百枚、いやもしかしたら千枚を超えるほどの量に見えた。
「本当に映画好きなんだな」
呟くように僕が言うと、田中も僕の視線を追って本棚を見た。
「俺も大学の頃はよく観てたんだけどな。時間もたくさんあったからさ。でも社会人になってからは全然観れてないなあ」
「……横井さん、忙しそうですもんね」
ようやく田中が口を開いた。
「よく仕事終わった後に映画観る気力あるよな。難しい映画とか絶対観れないよ俺」
「……逆ですね。難しい映画とか観て、考え事したいんです。なんか、その日あった嫌な事とかも忘れられる気がして」
田中の言う「嫌な事」が何を指すのかが気になったが、ここは慎重にいかないと、と思った。田中がいつもより少しだけ饒舌なのは、自分の部屋にいる安心感も手伝ってのものではあるだろうが、間違いなく「映画」がきっかけだろう。
「そうだ、田中のお薦めの映画って何?DVD見せてよ」
「え」
田中が驚いて僕の方を見た。そんなにびっくりすることだろうか。
「わかりました」
田中は少し考えて、おもむろに背後の本棚の中を漁り始めた。
──思ったより、元気そうじゃないか。僕はいつもより機敏に動く田中と、そして本棚の中のDVDを興味深く眺めた。
本棚の一段目には写真立てがあり、数人の男女が笑顔でこちらを見つめている。
「大学の頃の写真?」田中の背中に問いかけた。しかし田中はDⅤDを探すのに必死なのか、聞こえていない様子だった。
「これ、どうでしょうか」
田中が声をかけてきたのはそれから五分くらい経ってからだった。田中の手に一枚のパッケージが握られている。
受け取ると、『それでも夜は明ける』 というタイトルが記されている。
2013年イギリス・アメリカ合作映画。原題『12 Years a Slave』。誘拐され奴隷として売られた自由黒人の男の、12年間にわたる壮絶な実体験を映画化。ゴールデングローブ賞「作品賞」ほか多数の映画賞を受賞。
「全然知らないな、どんな話?」
「一言では難しいですけど……簡単に言うと、奴隷に間違われた自由黒人の主人公が、12年間強制労働を強いられる中で、それでも希望を失わない様子を描いた作品です」
その説明を聞く限りでは、随分と重苦しい作品であるように思った。間違いなく、僕ならば観ようとは思わない類の作品だろう。
「いいね、面白そう」
僕がお世辞を言うと、田中はこくんと頷いてパッケージからDVDを取り出し、テレビの方へと向かった。
「え?」
──今からこれを観るってことか?しかも、二人きりで。
すると、田中もまた驚いた表情で僕の方を振り返った。
「あ、いや、なんでもないよ。俺、この席で良い?」
田中の表情を見て、概ねの状況を理解した。「DVD見せてよ」という僕の尋ね方が紛らわしかったのと、田中の早とちりによるすれ違いだった。(普段の仕事でも、たまにこういうことあったな)──つい数日前のことなのに、なぜかそれらのやり取りが懐かしく感じられた。
「ええ。──何か、飲み物要りますか?」
「おかまいなく」
そう言って、僕は田中に微笑んでみせた。
もしかしたら、この機会が良いストレス発散になるかもしれない。僕も、田中も。
5
映画は二時間弱だったが、僕にはもっと長く感じられた。
全体的に話のトーンは重く、過剰な演出も一切控えられていたので、抑揚が無く退屈だった。要所要所で分からない箇所もあり、その都度田中に説明を求めた。田中は僕の質問に一つ一つ丁寧に、そして的確に答えてくれた。
映画を観ている最中、しきりに純の顔が頭を過ぎった。純の好きそうな映画だったからだ。彼女は観たい映画があると念のため僕を誘うのだが、彼女のチョイスはどれも難解で、大抵の場合は彼女が一人で映画館へ足を運ぶ。意味を解さない人間がついていったところで、彼女の気分を害するだろうという僕の配慮だった。
だけど、目の前で活き活きと映画を解説する田中を見ていると、そんな自分の配慮がひどく的外れなものにも思えてくる。ひょっとしたら純は、僕とこういう会話を交わしたかったのではないか。
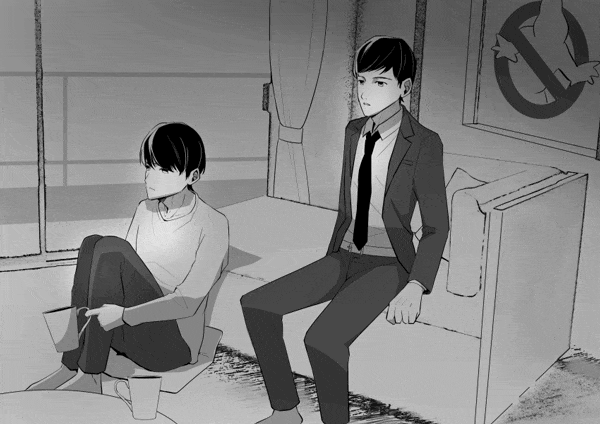
「どうしたんですか横井さん」
田中に声をかけられ、自分が随分と険しい顔をしていたことに気づく。
「いや、何でもない。ごめん、正直俺にはよく分からなかった。でも、田中の話はすごく楽しい」
少し気恥ずかしかったが、そう言った。
「……田中さ、会社でもそういう感じで話せばいいのに。正直もったいないよ」
田中はしばらく黙っていたが、やがて意を決したように口を開いた。
「会社では、なかなかそうはいきませんよ」
「どうして?」
「…僕も、自分らしく振舞いたいと思っています。でも、今の職場でそれは無理です。僕にとって仕事は、まだ自信を持って出来るものではないので」
「それは、少しずつ慣れていけば」
田中はうーん、と言うと、しばらく部屋中に視線を泳がせた。まるで空気中に漂っている言葉をかき集めているみたいに。
「たとえば伊藤さんはさ、ああいう性格もあって結構ズバズバと意見を言うじゃない?
俺はそれが伊藤さんのいいところだと思ってるし、すごく助けられてる。
田中も伊藤さんのようになれとは言わないけど、思い切って意見をぶつけてくれれば、俺は受けとめるよ」
「でも、伊藤さんも横井さんに言えてないこと、いろいろあると思います」
「え?」
驚いて訊き返したが、田中は何も言わない。
「どういうこと?」
僕が再度尋ねると、田中は言いづらそうに口を開いた。
「横井さんのプロジェクトに対する思い、僕も伊藤さんも分かってます。分かってるからこそ、言い出しづらいんです、自分の意見を。
この前、プレゼン会議の後、二人で飲みに行ったんですけど、伊藤さんも自分なりの考えがあるって言っていました。
でも、『それでも今は、横井さんの思いを尊重しよう。そのために私たちはサポートしなくちゃ』って」
「俺はもっと二人に自分の意見を言ってほしいと思っているよ、チームなんだから」
伊藤の知らない一面を知らされて軽い衝撃を受けながらも、僕はなんとかそう切り返した。
「横井さん、『そういう考えもあるよね』ってよく言いますよね。伊藤さんや僕が何か意見を言ったときとか。
でも、大体いつもはぐらかされて、最終的には、横井さんの意見を前面に押し出されてきて…」
それについては、思い当たる節があった。たまに彼らの意見を聞きながら、正直まだまだだな、と感じる時があった。でも、田中も伊藤もまだ2年目社員だ。見えていないところ、考えの及ばない部分も少なからずあると思っていた。
「きっと、横井さんからすれば僕の考えやアイデアはあまり参考にならないんだろう。横井さんはもっと色々考えているんだろう。──それは解っています。
でも、そんな状況で、どう自分に自信を持てば良いんでしょうか」
今度は僕が沈黙する番だった。田中の問いに、どう応えれば良いか分からなかった。
数時間前に野津部長から言われたことを思い出した。
── それは、マネージャーの働き方じゃないんだよ
しばらくの間、僕と田中は黙ったままだった。
「…ごめん、分からない」
ようやく、僕は田中にそう応えた。田中の表情から、みるみる落胆の色が見えはじめる。 「だから、」僕は語気を強めて続けた。
「これからどうしていけば良いか、一緒に考えてくれないかな?」
──それから、田中と色々な話をした。プロジェクトの内容から、これまでの進め方について、そしてこれからのことについて。はじめは黙って聴いていた田中も、少しずつ言葉を選びながら、思っていたことを話し始めた。
プロジェクトのこれからの展開について、田中はあるプランを提示してくれた。最近のトレンドでよく見られる手法だが、そこに少し演出を加えるだけで全く新しいサービスに見せることができる、と彼は言った。
「すごいな。そんなことまで考えてたのか」
「もとは、伊藤さんのアイデアだったんですけどね」
田中が少し照れ臭そうに言った。
話を聴きながら、田中がここまでプロジェクトのことを考えていたことが意外だった。同時に、嬉しくもあった。そしてどちらも、そう感じられたのはこれが初めてだった。──つまり、僕は彼のことを分かっていなかったのだ。
「明日さ、会社で伊藤さんと今のアイデアについて、じっくり話し合わないか」
僕はそう提案してみた。──まだ言っていないこともある。プロジェクトのリーダーが、僕ではなくなる。そのことも二人に伝えなくてはいけなかった。
でも、もしかしたらその方が田中と伊藤にとって仕事にやりがいを見出せるいいチャンスかもしれない、もっと良いプロジェクトにしていけるかもしれない、と思った。
「はい。…──すみませんでした」
田中は力強く返事した後、少しだけトーンを落として謝った。
「なにが?」
「3日間も休んでしまったこと。それに、こうやってわざわざ来てもらって」
「その分、明日から頑張ってもらうよ。──覚悟しとけよ?」
僕は田中の肩を軽く小突いた。田中は今日一番の笑顔を見せた。
家に着くころには日付が変わる間際だった。気のせいか、部屋の中はまた少し物が減ったように感じる。
純が残りの荷物を取りに来て、作業がすべて完了するのはいつ頃になるのだろうか。一週間か、三日後か、
もしかすると明日にはもう一区切りついてしまうかもしれない。そう思うと、梱包された箱をひっくり返し、再び荷物を散らかして彼女の準備を遅らせてしまいたい衝動にも駆られた。
彼女がまとめた段ボール箱の側面には、丁寧な字で『食器』『雑貨』『化粧品』などの分類が記されている。それらの文字を何気なく指で辿っていくと、段ボールの山と山の間から、モンステラの鉢が姿を現した。
モンステラのその大きな葉は、僕に手を差し伸べてくれているようにも思見えた。そして、僕もそうやって、誰かに手を差し伸べられるような人間に変わりたいと思った。
田中が自分らしく振舞えるために、僕に何ができるだろう? そして、純のためにできることは何だろう? 僕は彼らの何を見てきて、何が見えていなかったのだろう。田中らしさ。純らしさ。そして何より僕らしさ――。
問題は山積みだ。しかし、一つ一つ片づけていこうと思った。如雨露に水を汲み、「水やり忘れててごめんな」と語りかけ、モンステラの根元を湿らせていく。
このモンステラが枯れてしまわない限りは、僕のその願いも、叶えられるチャンスがあるかもしれない。
──そんなことを思った。
[続く]
<スポンサーリンク>

