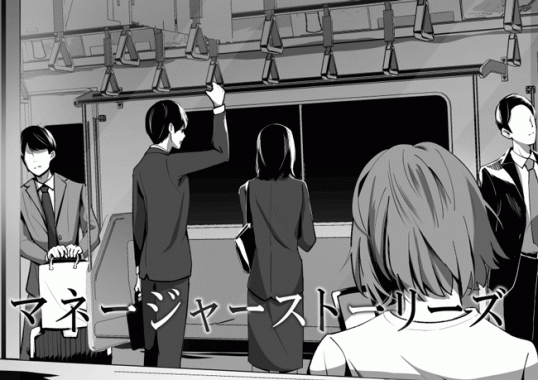
第4話 – 本当のこと
人でも、犬でも猫でも、とかげでも、小鳥でも
「後ろ姿」をいいなあと思えたら、
それは「好き」だってことだと、思います。
糸井 重里
「ボールのような言葉」より
1
「春からプロジェクトの一員としてご苦労様でした。伊藤さんの働きぶりは僕自身も見てきましたし、途中から引き継いだ井田さんからも聞いています」
ミーティングスペースのテーブルに対面に座っている、やや俯きがちな彼女──伊藤に向かって、僕はそう伝えた。
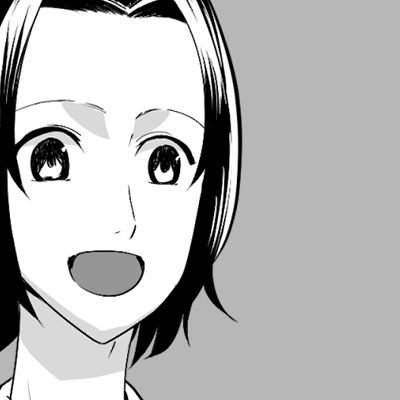
「メディア企画開発部一課」アシスタントディレクター。横井の部下。横井を慕っている。自称「猪突猛進型」で、考えるよりまず先に行動する。喜怒哀楽の表現が豊かで、それが長所でもあり、時には短所にもなると横井は考えている。
伊藤との評価面談が始まってすぐに、彼女の様子がいつもと違うことに気付いた。元気がない──、というよりも、距離感だ。
彼女は、いつも相手の表情を覗き込むように顔を近づけて話す。だけど今目の前にいる伊藤は僕から距離を取ろうとしているかのように、机から少し離れて椅子に腰かけていた。

「メディア企画開発部一課」マネージャー。
この春に昇格したばかりで、自身もこれまでの業務とのギャップに戸惑いつつも、新規企画立ち上げに向けて部下たちと協力し、奔走している。
「人の気持ちを察することに長けている」とは本人の談。年下の恋人・純との結婚も考え始めている。
「伊藤さんはこの半年間、自分でどう評価しているかな」
僕は、沈黙を続ける彼女にそう尋ねた。
伊藤は「うぅん」と短く唸った。その仕草は「考えているフリ」をしているようにも見えなくはなかった。本心はどこか別の、深い場所に隠しているみたいに。
「伊藤さんが書いてくれた自己評価は、自分のことをきちんと客観的に見られている印象を受けたよ。冷静な判断が出来ているよね。コミュニケーション能力の高さは素晴らしいと僕も思ってる。ただ、ここだよね」
僕はシートの該当箇所を指差した。『業務の改良・改善』、そして『企画提案』の二つだ。
そこには伊藤の自己評価で「1」という数字が打ち込まれていた。評価シートに顔を向けたままの彼女とは視線が合わない。シートの内容を見直しているのだと思い、そのまま話を続ける。
「ここを伸ばしていくためにも、伊藤さんにはもっと前面に立って業務に取り組んでいってほしい」
「はい」
返事はしたが、相変わらず心ここにあらずに見えた。そしてその様子は、僕を段々と不安な気持ちにさせていく。
──だが、今は面談中なので話を進めるしかない。
出来るだけ簡潔に話すようにしようと考えながら、あらかじめメモしておいた改善点を口にした。
「遅行よりは拙速とも言うけど、小さなミスがたまに目立ってしまうときがあるね。こういうのは確認も大事だけど、先を見越せる視野を持てるようになると減るはずだから、そういった意識も必要だと思う。
ほら、今はアシスタントとして業務に取り組んでもらっているけど、将来的には伊藤さんにも部下が出来て、そいつらをリードしていく立場になるだろうし、その準備だと思ってもらえたら」
「はい」
伊藤は相変わらず評価シートを見つめたままだ。膝の上に置かれた手が、何かメモを取る様子もない。
まるで手触りの無い会話は(この場合、会話と言っていいのかすらも怪しかった)、先日の純とのやり取りを彷彿とさせた。

横井の恋人。文房具会社に勤めており、サバサバとした性格ながらも人望は厚く、仕事も速いキャリアウーマン。しかし家(横井の前)ではそのスイッチが切れ、片付けも疎かにするなど、ズボラな一面も見せる。
ほとんど勢いに任せて僕が「会いたい」と口走り、通話口で純が息をのむ気配が伝わってきた。僕は動揺を抑えきれず、思わず電話を切ってしまったのだ。
しばらくベランダで頭を冷やしているうちに、自分がとんでもない過ちを犯したような気がして、慌ててかけ直したところ、二コール目で彼女は出た。純としても、突然のことにうろたえ、同じように携帯を手にしていたままだったのかもしれない。
そんな風にして、お互いに急くようにやり取りを再開したのとは裏腹に、ほとんど無意味な沈黙だけを共有し、ようやく僕が発した言葉は「さっきはごめん」だった。
「ううん……私の方こそ……」
しかし、純は最後までその続きを言わなかった。
「最近、なんか思いつめているようだし、もし悩みがあるなら」
僕は再び伊藤との評価面談へと意識を戻して、そう尋ねる。
「え?」
伊藤はようやく顔を上げ、僕の顔を見た。一瞬どきっとしたような表情は、落胆したそれに変わっていく。
おそらく、彼女の目には失望した表情の僕が映っていたことだろう。その失望が、彼女に向けられたものだと誤解されるのを恐れた。僕は自分自身に失望していたのだ。目の前の部下に対して、前向きな言葉ひとつかけられない自分に腹が立っていた。
「最近、何か困っていることがあるの?」──もう一度だけ、彼女にそう訊いた。
「いいえ、大丈夫です」
「そうか。それならいいけれど。まあ、今日はちょっと厳しいことを言ったかもしれないけど、伊藤さんにはこれまで助けられたこともたくさんあったから。もう少し、自信を持って。期待しているので頑張ってください」
「はい、わかりました。ありがとうございます」
僕の気休めにもならない励ましを、終了の合図だと受け取ったのだろう。伊藤は重そうに腰を上げた。それ以上、何を言ったらよいのかわからない僕も、つられて腰を上げた。
「あ、それから」
僕はミーティングスペースから退出しようとする彼女の背中に向かって、声を掛けた。
「はい?」
伊藤が振り向く。
「午後からの出張は14時前にここを出よう」
今日は伊藤と本厚木まで日帰り出張に行く予定だ。
「わかりました」
彼女は小さく頭を下げ、「失礼します」と言いながら、その場から立ち去っていった。
2
伊藤との面談を終えると、僕は井田のところへ向かった。運よく席にいて、手も空いているようだった井田を僕はミーティングスペースに誘った。
「どうした、突然」
少しだけ憮然とした表情を見せながら席に着いた井田に、「伊藤のことだけど」と切り出した。
「伊藤がどうした」
「今日、評価面談をしたんだけど、様子がおかしくてさ。最近、そちらでの様子はどうだ?」
「おかしいって、どんなふうに」
井田は首を傾げた。
チーム外の人間に面談内容を話すことは出来ない。だけど井田は彼らのリーダーだから、どのみち報告する相手だ。僕は彼女との面談での様子をかいつまんで話した。
「ちょっと厳しい内容だったのは間違いないんだけど、なんか上の空という感じで、こっちの話も聞いているのか、よくわからなくて。前はあんな感じじゃなかったと思うんだ。失敗しても、へこたれないというか、打たれ強いというか、そんな感じだったような気がするんだけど、何か落ち込むようなことでもあったのかな」
井田は僕の話を聴き終えた後、少しだけ姿勢を崩し「うーん」と呻った。
「たしかに、ここ最近、あまり元気のある様子ではなかった。けど──」
「けど?」
「うん。──そうやって、あからさまに態度に出たというのは、珍しいかもしれないな。なんというか、伊藤らしくない」
「たしかに」
僕は井田に同意した。たしかに、彼女らしくない。井田はまだ何かを考えているのか、腕を組んで上空を見つめている。
「どうした?」
僕の呼びかけに、彼は諦めたようにため息をついて、ゆっくりと言った。
「これは、思い過ごしかもしれないけれど。
──以前から少し気になっていたことがあって」
「だから、なんだよ」
「伊藤はお前に憧れているというか、好意を持っているのかもしれない」
3
伊藤が部署に配属された一年前、僕は彼女の直属の上司として、よく商談先へ一緒に赴いたものだった。
はじめは僕が手本も兼ねていたのだが、配属から三か月が過ぎたタイミングで、伊藤をメインに、次第に僕は補助側に回るようになった。それくらい、彼女の飲み込みは早く、やがて一人で商談先へ送ることにも不安は無かった。
しかし、伊藤が一人で商談先へ向かったある日、伊藤がミスを犯した。
彼女からほとんど泣き出しそうな勢いで電話がかかってきたので、まずは落ち着かせるのに必死だった。
背後で電車のアナウンスが聞こえたため、おそらくどこかの駅からかけているのは察しがついたが、尋ねると、商談の際に使用する予定だった資料一式を自宅に忘れてしまったということだった。
資料のデータは伊藤のPCに入っている。とすれば、近くにあるキンコーズで印刷すれば良いだろう。──ただ、商談先企業との打ち合わせの時間までもう15分もなかった。
急いで僕も現地に向かい、移動中には先方に遅れる旨の連絡を入れ、伊藤には印刷対応の指示出しを行った。伊藤と合流したとき、彼女は印刷し直した資料を確認し終えたところだった。
そして駆け足で商談先に辿りついたときには、当初予定していた時刻より30分も遅れていた。
担当のお客様は僕らのミスを笑って許してくれたが、商談の結果は芳しくなかった。
帰りの電車で伊藤は、分かりやすいほどに項垂れ、吊革をぎゅっと握りしめていた。
ようやく一人で仕事を任されるようになった矢先に、よりにもよって入社間もない社員のような凡ミスを犯してしまったのだから、彼女の胸中は痛いほどよく分かった。
「俺も伊藤さんくらいの時に、同じようなミスをしたことがあるよ。営業で使う大事な資料を、家に置いていっちゃってさ。書類を忘れたこともそうだけど、大事な仕事を家に持ち帰ったことも、後ですごく叱られてさ……そん時は野津部長、まだ部長じゃなかったけど、一緒について行って仕事をしてたんだけど、悔しかったなぁ。早く認めてもらいたかったんだよね。だからとにかく毎日がむしゃらにやって、体力的にも精神的にもいっぱいいっぱいの状態だった」
地下鉄の窓外は暗く、隣に立つ伊藤に、というよりは、窓ガラス越しに目が合う彼女に向け、僕は話した。
「野津部長は、あまり褒めずに部下を育てるタイプでさ、要は『自分で感じ取れ』って背中で語る感じ。でも俺は、本当はこう言ってほしかった。『どうってことないよ』って。伊藤さん、どうってことないよ」
ガラス越しに、伊藤が目元を拭うのが見える。
「失敗したってことは、それについて正面からぶつかったって証拠だよ。そういう人が、最後に成功する。俺みたいにね」
最後は冗談のつもりで言ったのだが、伊藤が笑わなかったので随分と恥ずかしかった。
4
横井さん、どうしたんですか?
横に立つ伊藤に尋ねられ、ふと我に返る。新宿駅で乗り換え、今は小田急線の車内だった。本厚木までは、あと30分ほどはかかる。
「いや、ちょっと昔を思い出して」
「そうですか」
それきり、伊藤は黙り込んだ。気まずい空気は相変わらずだった。
車内は近くの学生たちなのか、私服姿の若い男女が多く、比較的賑やかだった。扉付近に立つ若い男の子が何か冗談を言ったのか、横に立つ女の子が彼の肩を二回叩いた。
窓外の景色は、新宿駅から離れるほど、少しずつビルの数が減り、反対に人家や緑の数が増えていく。どこか牧歌的とすら言える景色だが、都心からほんの数十分、電車に揺られただけなのだ。そのことが今さらながら、少し不思議だった。
「そういえば伊藤さんは、大学の頃サークルとかやってたの?」
伊藤は「いえ、」と話しかけて、小さく咳払いをした。
「私はほとんどバイトばかりしてました」
「何のバイト?」
「ファミレスです」
伊藤が制服を着て接客をする姿はとても様になっていただろうと思う。そのことを言うと、「いえ、ホールじゃなく、キッチンの方です」と言った。意外な答えだった。そう思っていると彼女が「意外ですか?」と尋ねてきた。
「いや……まぁ、なかなか女の子では珍しいよね?」
「はい、私くらいでしたね。でも別に、ホールの子とも仲良かったですよ。シフト合わせて帰りは一緒に帰ったり」
「へぇ、そうなんだ」
「なんか、女子大生らしい会話、みたいなのってあるじゃないですか」
伊藤の言わんとしているところは、何となく分かる気がした。
「『〇〇くんカッコいいよね~』『最近、〇〇くんとうまくいってるの?』『何そのバッグ、どこで買ったの?』……私も最初はそんな感じでしたよ。でも、私はもともと勉強がしたくて大学に入ったので。そういう子たちって、勉強のことは二の次なんですよね」
先ほどとは打って変わって、伊藤は饒舌になった。僕は伊藤の学生生活について考えた。
僕はどちらかと言えば伊藤の言う「勉強なんて二の次」の学生だったから、伊藤の学生生活の過ごし方は少し寂しく思えたのだが、当の伊藤にそんな様子はなく、感傷的に昔を懐かしがるというよりは、かつての出来事を淡々と報告している、といった趣が強く感じられた。
「横井さんは、大学の頃の友達と、今でも会ったりしますか?」
「あぁ、そういえばいつからか全然連絡しなくなったなぁ」
伊藤に聞かれるまで、特段意識したことがなかった。
「やっぱりそうですよね」
伊藤はどこかほっとしたような様子で、そう言った。
「電車って、なんか不思議な感じしませんか?」
「電車?」
唐突に話題が変わったので、話の意図が掴めなかった。
「前に進んでいるんだか、同じ場所をぐるぐる回っているんだか……時々よく分からなくなることがあります」
車内アナウンスが、町田駅に到着したことを告げ、大勢の客が乗り込んできた。車内はほとんど満員に近い状態になり、その後は会話を続けることが何となく憚られた。
5
本厚木駅には時間通りに着いたのだが、出張先のオフィスが思いのほか駅から離れており、慣れない土地に伊藤と二人、随分と苦戦した。
駅前はそれなりに人波が絶えなかったが、徒歩20分圏内に位置するオフィスへ近づくにつれ、徐々に人の数は少なくなった。
結局、オフィスへ到着したのは約束の五分前だった。
先方は四十代後半の細身な男性で、柔和な笑みと話し方は、何だか片桐さんによく似ていて親しみを覚えた。
商談は滞りなく進んだ。
今回は僕がメインとなって話を進めたが、先方が随分と伊藤のことを気に入った様子で、次回からは伊藤に任せても平気だろうと思った。
伊藤は先ほどまでの思いつめた様子を一切感じさず、終始笑みを絶やすことなく積極的に議論に参与していた。
およそ二時間の商談を終え、僕らがオフィスから出たとき、時刻はもう六時を過ぎていた。薄暗さを増した通りには人が一人もおらず、通りを挟んだ向かいの路地の灯りが随分と寂しく映った。
行きの時は大分苦労したが、駅までの帰道はさほど難しくなさそうだった。
「それにしても」
いつも会社から自宅まで歩いている街並みとここでは、かなり景色が違って見えた。つまるところ、活気がない。
もう夕刻だからということもあるだろうが、ほとんどの店のシャッターは閉ざされていた。見れば畑なんかもあちこちにあり、よく言えばのどかな風景が広がっている──といったところだ。
ただし夕陽が沈みかけたこの時刻では、どうしてもそこに「うす暗さ」を感じてしまう。更には、空には重苦しい雨雲が広がっていた。
(……今日は、たしか晴れだったはずなのになぁ)
嫌な予感がして、僕は歩く速度を速めた。けれど、すぐに元の速度に戻した。
「ごめん。歩くの速すぎたよね」
「いえ、大丈夫、です」
とはいえ、伊藤の息は少し上がっていた。僕はゆっくり歩くように意識して、伊藤の横に並んだ。
「すみません」
「何が?」
「歩くペース、合わせてもらって」
「…いや、俺の方こそごめん……ヒールって歩きにくいんでしょ?」
以前同じことをして、純に叱られたのを思い出した。
「ちょっと雲行きが怪しいのが気になってさ。晴れる予報だったから、傘持ってないんだよ」
「私もです」
「駅まであと半分ってところなんだけど。間に合うかな」
僕はポケットからスマホを取り出し、地図アプリを起動しようとした、そこにぽたりと水滴が落ちてくる。
「あぁ、降ってきたね」
今の調子だと、駅に着くまでに15分以上かかるはずだ。雲はどちらかというと駅側の方からきている。進めば進むほど雨足が強くなることは明白だった。
「適当に喫茶店にでも入って、雨宿りしたほうが良いかもしれないね」
伊藤の返事を待つことなく、僕は雨を凌げそうなところはないかと辺りを見回した。だが、喫茶店どころか開いている店自体見当たらない。しばらく歩き続け、ようやく店らしき灯りがあると思って目を凝らせば、それは精米の自動販売機だった。
僕はもう一度スマホを見た。すると駅とは反対に数百メートルほど進んだところに、居酒屋があるのを見つけた。

「横井さん、そっちは駅から離れませんか」
「そうなんだけど。こっちの道をしばらく行くと、店があるみたいなんだよね」
「何てお店ですか」
スマホのナビを見ながら、僕はよく知られたチェーン店の名前を口にした。すると伊藤も鞄から自分のスマホを取り出した。手早くタップしているのは、おそらくこのあたりの地図を呼び出しているのだろう。
「……それって、ここからかなり離れませんか」
「ちょっと離れるけど、確実にわかるところがよくない?」
伊藤は無言でスマホをタップし続けていた。その間にも、雨は勢いを増している。僕は、急かすように伊藤の名前を呼んだ。
「横井さん、駅方向にもう数十メートル行ったところにも、お店ありそうですよ」
言われて自分のスマホを確認する。伊藤の言う店は、確かに僕のスマホにも載っていた。
「でも、聞いたことない店だし、どんなとこか分からないよ」
「雨宿りだけですし、それでもいいんじゃないですか?」
「そうだけど……」
伊藤の表情を見て、僕ははっと言葉を飲んだ。
(純も、こんな顔をしていた時があったよな……)
眉に力が入っているような、頬が強張っているような、硬い表情。不満を口にするわけではないけれど、何か思うところがあるのかもしれない。
何か言いたいことがあるならきちんと口に出してくれればいいのに。 午前中の評価面談のこともあって、彼女の不遜な態度が妙に気になってしまった。
──結局、彼女の意見を尊重して駅へと向かうことにした。
「伊藤さん、さっきの評価面談のことで、もうちょっと話し合っておいた方がいいかな、と思ったんだけど」
雨に濡れながら、ふと伊藤にそう話しかけた。彼女から硬い空気が伝わってきた。
「伊藤さんは、今の仕事してて楽しい? もちろん、嫌々やってるように見えるってわけじゃないんだろうけど。なんていうか、何か悩んでいるようにも見えるから」
――伊藤は、仮面を被って仕事しているように見える時があるんだよな
井田に言われた言葉を思い出す。田中だって、仕事に不安や不満があったのだし、伊藤にだって何らかの思いはあるのだろう。
その「仮面」をとりのぞいてあげたい──そんな気持ちが、僕の胸の中で急に、強まっていったのだ。
「伊藤さんが一生懸命なのはちゃんと伝わってるよ。積極的に関わっていこうと考えていることも、僕や、井田にはわかっている。だけど、何か無理をしているようにも見えるんだ」
伊藤は無言で鞄を抱えながら、少しずつ雨足の強まってきている道を歩き続けている。僕は雨を避けるために右手を額にかざしながら、話を続けた。
「仕事で何か悩んでいるんだったら、相談してほしい。もし井田に言い辛いなら、僕に言ってくれても構わないし……もし同性の方がいいって言うなら、富岡もいるから。別のチームだけど、富岡もよく出来るし、女性としてのアドバイスなんかも色々聞けると思う」
「……横井さんは、私にどうなって欲しいんですか?」
伊藤は僕の方を見ずに、そう訊いてきた。
「どうなって、って……どんな風になりたいか、決めるのは伊藤さんでしょ?」
「でも、横井さんも井田さんも、私に求めている姿がありますよね、きっと」
雨のせいなのか、その声はいつもより低く聞き取り辛かった。それ以上に、僕には伊藤の言っていることが理解出来なかった。
「どういうこと?」
「私自身が何を求めているかなんて、横井さんには全然わからないでしょうね」
伊藤の声はさっきよりも大きくなっていた。
「別に分かってくれなくても良いんですけど。でも最近はちょっと、疲れてきちゃってて。 井田さんは田中君のフォローはしても、私のフォローはしてくれませんから」
「そんなことはないんじゃないの?井田だって伊藤のこといつも──」
「横井さんもですよ」
伊藤は僕の言葉を遮るように、そう言った。
「田中君が無断欠勤した時も、しっかりフォローしてましたよね。でも私には何もなかった」
「伊藤さんは無断欠勤なんてしたことなかったよね?」
伊藤は険しい表情のまま、僕の少し離れた位置を歩きつづけている。
「でもだからって、辛くない、悩んでない、ということにはならないですよね」
「だったら……」
「相談しようとしたことはありました。でも違う話題に挿げ替えられて、そのまま放っておかれて終わりです。聞き返されたことはありません」
一体いつの話だ。僕は記憶を辿ってみたけれど、そんなことをした覚えはなかったし、そもそも相談された覚えもなかった。
「普段の業務でもそうです。提案書を見せても『ちょっと違うんだよな』とか『そうじゃないんだよな』とか言いますよね。具体的にどうするといいのかは教えてもらえない」
「それは」
「自分で考える力をつけるのが理想ですよね。横井さんがそう考えているのはわかります。でも私は、どっちが前なのかわからない時に『そっちじゃない』しか言ってもらえなかったら、先には進めないタイプなんです。
──それでも頑張って進もうとして、でもそれは、周りから見るときっと、同じところをぐるぐる回っているんだろうなって。──実際そうなんでしょうけど。きっと、すごく要領が悪いんです、私って」
伊藤が話し終えると同時に、雨がまた一段と激しくなった。彼女の足取りが少しだけ早まる。今度は僕が伊藤に追いつくように、歩調を速めた。
彼女はしばらく無言だった。僕も、何も言わなかった。言葉が出てこなかった。
そのまましばらく歩き続け、ようやく道沿いに小さな看板をつけた喫茶店が見えてきたとき、僕は内心ほっとした。
6
「開いてるみたいだし、早く入ろう」
その喫茶店は、どうやら自宅一階を改装して造った、個人経営のようだった。どうりで聞いたことのない店名だし、口コミもなかったのか。しかし今となっては、味が良かろうと悪かろうと、雨粒さえ凌げればよかった。
カランと音のなる鈴がついたドアを開くと、儚げな間接照明の灯りと、挽いたばかりの珈琲豆の匂いが、僕たちを出迎えた。
店には愛想のよい笑顔を浮かべたマスターが一人いるだけで、他に客はいなかった。僕と伊藤は雨で濡れたスーツと身体をハンカチで拭きながら、案内された窓際の席についた。
窓の外では、大粒になった雨が地面で撥ねる音が聞こえた。
「災難でしたね」
気を利かせてくれたマスターが、ハンガーとタオルを持ってきてくれる。
「ええと、ブレンドで。伊藤さんはどうする?」
「じゃあ私も、同じものを」
借りたタオルでバッグを拭いていた伊藤は、ろくにメニューを見もしないままそう答えた。
僕たちは注文を伝えた後、コーヒーが運ばれてくるまで無言だった。
その間、僕は先ほどの伊藤の言葉を何度も反芻していた。彼女が助けを求めていたとは、思っていなかった。僕のフォローやアドバイスがなくても、自分で解決できると思っていたから。
伊藤は、じっと押し黙ったまま、うつむいている。
「──すみませんでした。さっきは少し、言いすぎました」
コーヒーを一口飲んで、伊藤はつぶやいた。
「ううん、謝ることないよ」
僕はコーヒーを一口飲んで続けた。
「悪いのは俺だし。伊藤さんが悩んでたことに全然気づかなかった。──マネジャー失格だな」
伊藤はなにも言わなかった。僕は何かを言わなくてはと思い、話し続けた。
「俺は伊藤さんに社会人として、今より更に成長してほしいと思ってる」
伊藤はまだ下を向いたままだ。
顔が見えない分、どんな風に受け止めているのかがわからない。また、的外れなことを彼女に言ってしまっているのだろうか。心配になりながらも、言葉を選んでいく。
「今はアシスタントだけど、将来的には俺の後を継げる位置までキャリアップしてほしいし、伊藤さんにはその素質があると思っているんだ」
すると伊藤がようやく、顔を上げてこっちを見た。
「横井さんにとっての成長って、『キャリアアップ』なんですか」
「僕にとって…というより、普通そうじゃない?」
「普通がどうなのかはわかりませんが、少なくとも私は、違うような気がするんです」
「……どういうこと?」
「働き方って、人によって色々ありますよね。私は自分の理想の働き方が出来るように、バランスを取っていきたいと思っているんです」
「理想の働き方って?」
いつの間にか、僕が訊く側になっていた。
「理想というと、ちょっと大げさかもしれませんが……、例えば私は、チーム内のメンバーと協力しあって業務を進めていきたいと、いつも思っています。そのためには前に立つ人も大切ですけど、誰かが後方支援する必要もありますよね。チーム全体をよく見て、平等にサポートしていけるような存在になりたいと最近考えるんです」
僕はカップを置きながら、再び腕をテーブルに乗せた。
「伊藤さんは、キャリアアップはまったく考えてないの?」
「まったく望んでいないわけではないです。ただ、そうですね……積極的に狙いたいわけでもないのかもしれません。こういう考えは、ダメですかね」
最後の方は弱々しい声だった。
「ダメとかじゃないよ。ただ、なんていうか、伊藤さんはいつも積極的に業務に取り組んでいるし、後輩の面倒もよく見てくれてる。だから、てっきり富岡みたいにリーダーとして活躍したいと考えているんだろうなと、思っていたんだよ」
「はあ」
彼女は僅かながら首を傾げた。どうやら、僕のその見立ては、彼女にとってまったく的外れだったらしい。
「ごめん……なんか俺、伊藤さんを勘違いしてたみたいだ。働き方にしても、俺と同じ考え方だと思ってた。……あんまり、良い手本を見せてやれてなかったね」
「いえ、そうじゃないんです」
彼女はやや強い口調で否定した。
「横井さんの働き方は、とても素敵だと思っていました」
──伊藤はお前に憧れているというか、好意を持っているのかもしれない。
井田の台詞が頭をよぎる。少し間をおいて、伊藤は再び話を続けた。
「だけどそれは、真似したいとか、そういうのではなくて。なんだろう……憧れ、みたいなものだったんですかね」
「……そうなんだ?」
「……なんか、本人を目の前に恥ずかしいですけど……横井さんの求めている理想の姿に自分を近づけようとしていたところはあると思います」
「…うん」
「でも、最近はだんだん辛くなってきて。『これって、本当に私が望んでた働き方なのかな?』って……」
伊藤は珈琲にミルクを足し、ゆっくりとかき混ぜ続けた。
「井田さんにも、悩みごとがあるのかって聞かれましたけど、話したところで解決するのかな、って思っちゃって。……なんだろう、疲れちゃったんですかね、私」
僕は、伊藤をすっかり誤解していた。同じ価値観を持っていると思っていた部下は、実はそうではなかった。一方で、そんな僕に対して、憧れも感じてくれていた。
──だが、「いる」ではなく「いた」と話す伊藤は、おそらくそれらの感情もまた、過去形になりつつあるのだろうと思った。
きっと、僕がここ数か月仕事で悩んでいた時に、彼女もまた、悩んでいたのだ。そして、その間僕らはそれぞれ、悩みながらも歩み続けて、知らず知らず僕たちは遠のいていた。
「伊藤さんはさ、皆のフォロー役になりたいってことだよね」
──僕は気を取り直して、彼女に尋ねた。
「そうですね。今はまだ、大したフォローは出来ていませんし、あまり助けにはなっていないんでしょうけど」
「そんなことないよ。そういうのも、大きな共同体の中では大切な役割の一つだと思う。
もしかしたら、そういう役割の人たちって、業務やプロジェクトの全体像というか、流れが見えると、より活躍できるかもしれないね」
「流れ、ですか?」
「ほら、サーファーが波を読むみたいにさ、ああいう感じって、業務やプロジェクトにもあるんだよね」
「……横井さん、サーフィンやるんですか?」
「……いや、一回もやったことないけど」
「なんですかそれ」
伊藤がぷっと噴き出した。今日はじめて見た、彼女の笑顔だった。
「でも、今までそういう風に考えたことありませんでした。そうか、全体の流れを把握していくと、細かい部分も見えてくるかもしれませんね」
伊藤は少し柔らかい口調になって、そう答えてくれた。どうやらようやく、彼女にとってまともなアドバイスができたようだ。
7
それから少しの間伊藤と話をしていて、ふと窓の外を見ると雨は止んでいた。
「あ、雨止みましたね」
伊藤も同時に気づいたらしい。
「うん。──帰ろうか」
そこから駅まではすぐに辿りつけた。そのまま一緒に電車に乗るものだと思っていたら、「私は寄り道して帰るので、ここで」と伊藤は言た。
「せっかくだから、こっちに住んでる友達と会う約束をしていて。終電前の、せいぜい1~2時間くらいなんですけど」
「飲みすぎて終電逃さないようにね」
僕はじゃあ、と言って右手を挙げた。
「はい!」
そう言って、伊藤は少し軽い足取りで、僕とは反対のホームへと去っていく。
彼女の後ろ姿が見えなくなるまで、僕はしばらくのあいだそこに立ち止まっていた。

伊藤は、これからどう変わっていくのだろう。
今日一日、午前中の評価面談からここまでの日帰り出張と、久しぶりに彼女と沢山話ができた。
だが、彼女の悩みや葛藤が、今日一日で解消された訳ではないだろう。それでも僕自身、彼女に対して抱いていたイメージに誤解があったこと、そして伊藤との間にあった「距離」に気付けたのは、素直に良かったと思えた。
伊藤のいるチームから離れた今、彼女の上司として何をしてあげられるだろう?
彼女はいつも笑顔で駆け寄ってきてくれた。僕の話を熱心に聞いてくれた。信頼できる部下で、これから先も、同じように情熱を掲げて、一緒に仕事をしていくのだろうと、勝手に思っていた。
「なんだ、それ」
──ふと、そんなつぶやきが口元から漏れた。帰宅途中の二人連れのサラリーマンがちらりと僕の方を振り返って、そして何ごともなかったかのように視線を戻してホームの階段を昇って行った。
[続く]
<スポンサーリンク>

