第1話 – 私を知らない、あなた
小さい頃は、「自分は何にでもなれる」と思っていた。
ジョブズやゲイツのようなビジネスマンにも、ディズニーや宮崎駿のようなクリエイターにも、それから、チャップリンやマイケル・ジャクソンのようなエンターテイナーにも。
でも、少しずつ年齢を重ねていって、「何にでもなれる」と思っていた領域は少しずつ狭まっていって。世の中を深く知れば知るほど、自分の可能性がどんどん萎んでいくような、そんな感覚だ。
社会人になって30歳間近になった今では、たまに人と話すことにちょっとした恐怖を感じるようになった。
「つまらないことを言ってしまわないか」だったり、それから、相手に「自分が取るに足らない存在」であることを知られてしまうのではないか、というような不安感。
もちろん、そんなネガティブな気分の時ばかりじゃない。ちょっとしたことで希望と夢で胸がいっぱいになって夜眠れなくなる日も、ほんのたまにだけど、ある。
たまに訪れる小さな幸せと常に感じている不安の毎日、ふとこんな疑問が浮かんできたりする。「何者かになんて、世の中の人全員がなれる訳じゃない。自分がそう思うのは、単なる驕りでしかないんじゃないか」──と。
でも、心のどこかでこうも思っているのだ。「僕が何者かになれる可能性は、まだ残されている──、諦めるな。今はまだ頑張るしかない」って。
でも、頑張るって?いったい何を、何に向かって、頑張っていけば良いのだろう?
──これから話す話は、僕が新卒で入社した会社で管理職に昇格してからの、ほんの数か月の間の出来事についてだ。
きっとそれらは、どこにでもあるような話なのかもしれない。ただ、この期間は間違いなく、僕にとってひとつの「通過儀礼」の時期だった。
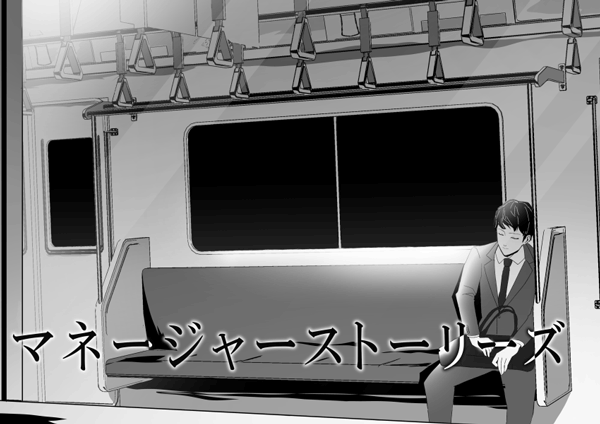
1
「自分にとっていちばん大切なことは、試合前に完璧な準備をすることです」というようなことを、いつだったかイチローが語っているのを見て、そりゃそうだ、おっしゃる通りだと思ったが、実際は準備に「完璧」なんてない。
一カ所を手直しすれば、また違う箇所が目につくようにできていて、どこかで線を引かなければきっといつまでだって終わらないだろう。
子供の頃から注意深かった僕は、その注意深さゆえに時に競争に出遅れたこともあるし、同様にその注意深さによって評価されたこともある。
この春からワークカラット株式会社の「メディア企画開発部一課」のマネージャーに任命されたのも、ひとえに僕の注意深さを買われてのことだろうと思った。
マネージャーになって最初の仕事は「新サービスの立ち上げ」だった。メディア企画開発部一課では、大小合わせて20のWebサービスを運用しているが、売り上げは徐々に下降の一途を辿っており、新サービスの立ち上げはいわば「起死回生の一手」というわけだ。
元来が注意深い性格の人間が、そのような責任ある立場になった時、一体どうなるか。僕の場合は、不思議なことにマネージャーになってからの方が肩の力が抜け「楽観的」になった。
たとえば、単純に仕事を捌くスキルで言えば、同期の井田の方が僕より遥かに優れていると思う。
淡々と、しかし着実に仕事をこなす彼は上司からの信頼も厚く、辞令が出た当初は「なぜ井田ではなく僕なんだ?」という戸惑いを抱かずにはいられなかった。

「メディア企画開発部一課」ディレクター。横井の同期。先に昇進した横井にライバル心を抱いている。同僚からの信頼も厚いが、会議などの場においての有無を言わせない的確な指摘に、周囲は恐れを抱いてもいる。
しかし、考えても仕方がない。最終的に任されたのは僕であるのだから、僕は自分なりの正しさを信じ、誠実に仕事をこなしていく以外に道はない。
自信はまるで無い。けれど「ダメで元々」という開き直りに近い心持ちが、ギリギリのところで僕を奮い立たせてくれている。
「横井さん、明日の打ち合わせをしなくても大丈夫ですか?」

「メディア企画開発部一課」マネージャー。
この春に昇格したばかりで、自身もこれまでの業務とのギャップに戸惑いつつも、新規企画立ち上げに向けて部下たちと協力し、奔走している。
「常に誠実であること」がモットー。恋人・純との結婚も考え始めている。
斜め前のデスクに座る田中が、不安そうな表情でそう語りかけてきた。

「メディア企画開発部一課」アシスタントディレクター。自分の意見を発信するのが苦手で、大勢の会議の場となると沈黙することがほとんど。大の映画好き。
「そうだな、一回通しでやっておくか。伊藤さんも大丈夫そう?」
隣に座る伊藤が
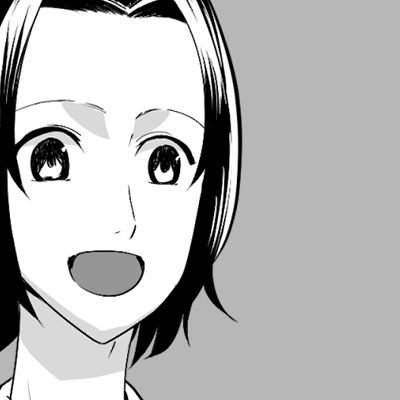
「メディア企画開発部一課」アシスタントディレクター。自称「猪突猛進型」で、考えるよりまず先に行動する。周囲との調和を重んじ、自らが調整役となることも少なくない。
「はい!私もちょうど、そう思ってたところです!」
と言うなり、席を立ち真っ先にミーティングルームへと駆けこんでいった。二人の部下にとっては明日は初めての企画会議となる。いろいろと不安もあるだろう。
しかし経験上、事前の準備を綿密に行えば行うほど、小さな綻び一つが大きな不安へと変わり、不穏な空気を当日にまで持ち込んでしまうことも僕は知っていた。
あくまで、前日の準備は確認程度に。イチローだってきっと、試合の前日はそのくらいの心持ちなのではないだろうか。
ミーティングルームを借り、全体の流れのリハーサルから、細かな改善点まで綿密に見直した。当日は企画概要を伊藤に説明してもらい、詳細は田中が説明する手筈になっていた。
軽い打ち合わせのつもりが、細かな調整を行ううちにすっかり時間が過ぎ、オフィスに戻ったころには人もまばらだった。
「あ、雨降ってきましたね」
傘持ってきてないや、と伊藤がぼやく。
晴れの舞台の前日が雨。ずいぶんとドラマチックな展開じゃないかと思った。
「横井さん、どうかしました?」
「いや、いいよ。最高。明日はいける気がしてた」
窓の外の曇天を見据えながら啖呵を切ってみせる上司を見て、二人の部下は困惑したように顔を見合わせたあと、明らかな愛想笑いを浮かべていた。
2
業務を終え、エントランスでエレベーターを待っていると、お疲れ様です、と後ろから声をかけられた。振り向くと、田中が肩をすぼめて立っている。
「田中も帰りか」
「あ、はい」
「家どこだっけ?」
田中は少し逡巡したのちに「西荻窪です」と答えた。エレベーターが5階に止まる。中には誰も乗っていなかった。
他に乗り合わせる人もおらず、僕と田中だけがエレベーターに乗り込む。田中はボタンの前に立ち、随分とまごつきながら「閉」のボタンを押した。そんな彼の後姿をぼんやりと眺めていると、彼の左の耳にピアスの跡があることに気づいた。
「明日、緊張してる?」
僕が尋ねると、彼はボタンを見つめたまま「少しだけ」と答えた。田中は首の後ろを執拗に揉んでいる。
「まあでも、できる限りの準備はしてきたわけだから。とにかく後悔無いように出し切ろうな」
努めて明るい声を出したつもりだったが、乾ききった密室の空気に、たちまち吸収されていくようだった。
1階のエントランスを抜けると、外の雨はだいぶ弱まっていた。道行く会社員は、傘をさしている人と、傘は持たずに伏し目がちに歩く人のどちらかだった。僕は傘を持っていたが、田中は持っていないようだった。
「どうする? 俺、一駅先だから歩いて帰ろうかと思ってたけど」
これから帰宅する彼のために、傘を貸してやるつもりでいた。一駅分くらいなら多少濡れてもどうにかなると思ったし、何よりこのまま田中と一緒にいることに居心地の悪さを感じてもいた。
田中はこちらが不安になるほど沈黙し、しばらくして「じゃあ、僕も次の駅まで歩きます」と答えた。
「そうか……わかった」
傘を田中の方へ傾けると、彼は小さく手を振ってそれを辞した。田中の真意が僕には分からなかった。
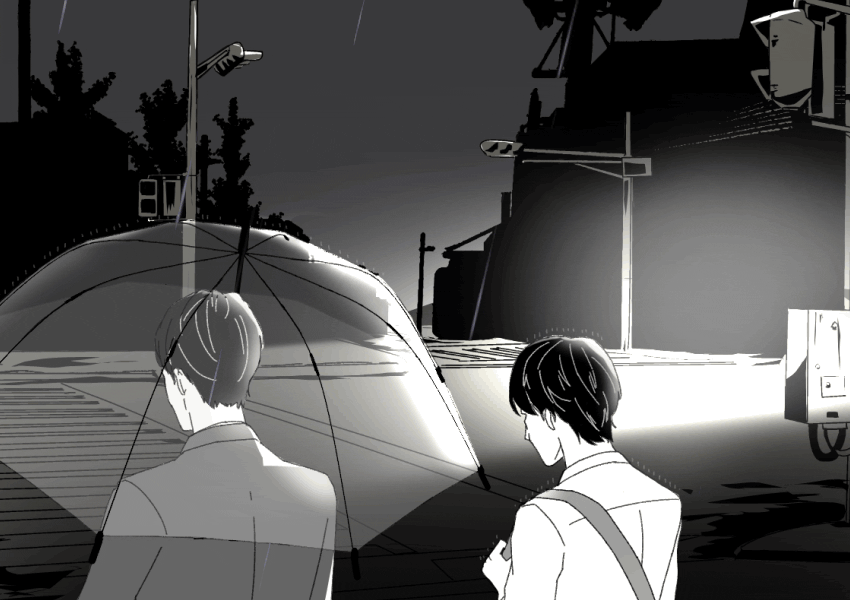
一つ目の交差点の信号が赤になり、僕たちは足を止めた。視界に入るのは同じように黒いスーツを着た会社員ばかりで、夜の空気も相まって、人々の影だけが一人歩きしているように見えた。
田中が何かを伝えようとしているのは分かったが、一向に話し出す気配は無い。彼の性格上、急かすようなことを言えばさらに口を閉ざしてしまいそうなので、僕は黙って待つことにした。
田中と伊藤は同期のアシスタントディレクターだが、二人の性格の違いは度々僕を悩ませた。
伊藤は快活でチームのムードメーカーのような存在だが、思い立ったら後先を考えずに走り出す癖がある。慎重に事を運んでいたなら起こりえない些細な漏れがよくあり、そのたびに彼女は眉を八の字に歪め謝った。
女性であること、そして彼女自身の性格を慮り、いつもある程度の境界線を引いてしまっているが、彼女のためにも一度本気で指導しなければいけないだろうと思っている。
一方の田中は、伊藤とは真逆の寡黙な性格で、とにかく自分の意見を表に出そうとしない。後で個人的に話をした際にはぽつぽつと考えを述べはするものの、大勢の会議の場などになると、途端に沈黙を貫いてしまう。
二人は同期のよしみで親しくしているようだったが、僕はそれぞれに別の接し方をしなければならないため、マネージャーの身としてはなかなか骨の折れる作業でもあった。
僕たちの前で信号待ちをしている中年男性が、信号の変わり切らないうちに歩き出し、横から滑り込んできたタクシーにクラクションを鳴らされる。よくある光景の一つだったが、隣に立つ田中が、クラクションの音に過剰に肩を震わせた。
「なにか悩みでもあるのか?」
とうとうしびれを切らし、僕は尋ねた。
「……今回のプロジェクト、僕は役に立てているのでしょうか?」
田中は今にも消え入りそうな声で、自分の爪先を眺めている。
「もちろん。すごく助かってるよ。田中がいなかったら、もっと時間かかっていただろうし、途中で計画自体も頓挫していたかもしれない」
信号が青に変わったので、僕たちは歩き出した。田中が何かを言ったが、雑踏の音でかき消されてしまった。僕は眉を上げ、上体を田中の方へ傾け、「もう一度言ってくれ」というニュアンスを表現した。田中が気持ちばかり大きな声で繰り返す。
「横井さんは、怖くないんですか?」
田中の声は震えていた。彼の性格を思えば、明日の会議はかなりのプレッシャーであるはずだ。
「そりゃあ、俺だって緊張してるよ。部署の売り上げがこの企画に懸かってるわけだし。もし受け入れられなかったらって思うと怖いな」
だけどさ、と慎重に言葉を選びながら後を続ける。「そうやって成長していくもんだろ? もちろん踏みとどまることなんて簡単だけど、前に進むこともない。人生ゲームだったら、ずっと振り出しにいる状態だよ。俺はそっちの方が怖いかな」
「そうですよね……明日、がんばります」
田中はぎこちない笑みを浮かべた。
「田中は休みの日とか何してるの?」
このまま重苦しい話題に終始するのも如何なものかと思い、僕は尋ねた。
「……いや、特に何も。映画を観るくらいですかね」
「じゃあ、あれ観た?」
僕は、現在公開中の大作映画のタイトルを口にする。
「いや、そういうのはあまり……」
「そういうの」が何を指すのかは明確ではなかったが、僕はなんとなく田中の言わんとしていることが分かったような気がした。いわゆる「娯楽映画」ではなく、単館劇場でかかっているような芸術性に富んだ作品を好むのかもしれない。僕自身はそういった作品の良し悪しは今一つ分からないのだが、純も田中と同様に単館映画が好きだったよな、と思い出す。彼女と田中は、ひょっとすれば話が合うのかもしれないが、ここで恋人の話題を出すのもどうかと思い、再び沈黙が続いた。
結局その沈黙を破ることはできないまま中野坂上駅に着いた。駅の雑踏の中に消えていく田中の背中はひどく小さく見え、すれ違う人波を不器用に避けながら消えていった。
3
マンションのエントランスへ入ると、同じように帰宅したばかりなのか、傘を畳むサラリーマンと鉢合わせた。
軽く会釈をしたが、向こうはそれを無視してエレベーターへと向かう。僕が郵便受けを覗いている間に、彼はさっさと扉を閉め上がっていってしまった。
玄関の扉に手をかけると、鍵はかかっておらず、すんなりと開いた。純のパンプスが乱暴に脱ぎ捨てられており、僕は内心ドキリとした。彼女の帰宅を狙って誰かが押し入ってきたのではないか。そんなイメージが瞬間的に頭を過ぎった。
「ただいま」
急いでリビングのドアを開けると、純がソファに腰かけ、無表情にテレビの画面を見つめている。静かな部屋に、お笑い芸人の場違いな声が響いている。

横井の恋人。文房具会社に勤めており、サバサバとした性格ながらも人望は厚く、仕事も速いキャリアウーマン。しかし家(横井の前)ではそのスイッチが切れ、片付けも疎かにするなど、ズボラな一面も見せる。
「おかえり」
「あーよかったぁ……鍵開けっ放しだったから一瞬身構えちゃったよ」
「あ、ごめん。忘れてた」
そう答える彼女は、少し疲れているように見えた。
「……何かあった?」
「ん? うん、大丈夫だよ」
「そっか」
彼女は立ち上がると、キッチン台に立ち、コンロにかけた鍋を温め始める。
「ごめん、私も帰り遅かったから簡単なものしか作れなかった」
「全然いいよ。仕事大変なんだね」
「カズほどじゃないよ」純は笑って、寝室へ入ると、パジャマに着替えて戻ってきた。
「私ちょっと疲れちゃったから、先寝てるね」
「ご飯は?」
「いいや、あんまお腹空いてないし」
「そっか……」
食べないと体によくないよ、と声をかけようと思ったが、疲れが溜まった時の彼女は機嫌が悪くなりやすく、些細なことで口論に発展することもこれまで一度や二度ではなかったので、すんでのところで思いとどまった。
かれこれ付き合い始めて二年が経つが、平穏を保つコツは互いに干渉しすぎないことだと心得ていた。
「明日って、今日みたいに遅くなりそう?」
純が鍋の中身を皿に盛りつけながら聞く。
「一応午後から会議だけど、まぁそこまで長引くことはないんじゃないかな」
「じゃあ、もし早めに帰れそうだったら連絡して。ちょっと話したいことがあって」
「わかった。別に話なら今でもいいけど?」
「……今日は疲れてるから」
「そうだね、ごめん」
「ううん、おやすみ」
彼女が寝室へ引っ込むと、途端にテレビの音が馬鹿みたいに大きく聞こえ、彼女の眠りの妨げにならないよう、ボリュームを極限まで絞った。何を言っているのかまったく聞き取れなかったが、ずいぶんと身振り手振りの大きな芸人で、その動きを見ているだけで何となく面白かった。
◇◇◇
「働く二十代女性へのインタビュー」と題して、ある文房具会社に取材に向かった。そこで働いていたのが純だった。
「文房具が、その人にとっての記憶媒体になってくれたらいい」と、彼女は言った。手に取るたびに、それを使っていた頃の記憶が鮮明に蘇る、そんな商品がお客様の手元に届くといい。彼女の話はいずれも示唆に富んでおり、人を惹きつける魅力があった。
「お気に入りの文具はありますか?」
僕が尋ねると、彼女は「一つには絞れませんが」と前置きした後に、筆入れから様々な文具を取り出し、まるで自分の子供をあやすような眼差しで、それらについて話し出した。当初の予定より遥かに時間は超過してしまったが、そんなことはどうでもよかった。
彼女がボールペンを手にし、くるくると踊るように手元を動かすと、その先から文字の連なりが生まれた。均整の取れた行儀のいい文字は、彼女の性格をそのまま映し出しているようにも思えた。
「やっぱり、字が綺麗なんですね」
思わずそう言うと、彼女は「やっぱり?」と尋ね返し、小さく微笑んだ。あの瞬間から、僕は純に惹かれていたのかもしれない。
◇◇◇
すっかり音のなくなった部屋の中で、かつての記憶に思いを馳せていた。最近では互いに忙しく、同じ部屋にいるのにすれ違ってばかりの生活が続いている。
彼女が作ってくれたポトフを口に運ぶ。忙しい最中にも関わらず、彼女の手料理は相変わらず美味しく、味付けも的確だった。
彼女の少し思いつめた様子と、彼女が話したいことは何なのか気にならないわけではなかったが、まずは明日の会議をそつなくこなすことに意識を向けるのが先決だろう。
しばらくして寝室から純の寝息が聞こえてきた。その規則的なリズムは、彼女の几帳面な性格を表しているように感じた。
4
朝、会社のエレベーターホールで片桐さんの後姿を見つけた。片桐さんは僕にとって年上の部下となるが、気さくな性格で話しやすく、好感が持てた。エキスパート職としての経験も長く、業務上の相談も気兼ねなくできる。
「メディア企画開発部一課」ディレクター兼クリエイター。エキスパート職であり、横井にとっての年上の部下。のほほんとした佇まいで人望も厚いが、時折、的確なアドバイスを投げてくる。ヘビースモーカー。
出勤ラッシュはいつもホールが混みあっており、四基あるエレベーターでもさばききれず、長蛇の列だった。片桐さんは列の前方にいて、後ろから話しかけるのは気が引けた。遠目からだが片桐さんの後頭部には白髪が混ざっており、「やっぱり年上なんだな」となんとなく思った。
タイミングよく三基のエレベーターが同時に開き、コンベヤーで仕分けされるように均等に人が乗り合わせていく。扉が閉まる寸前に、タイミングよく片桐さんと同じエレベーターに乗ることができた。両肩を誰かに挟まれながら、首だけを後方に向け、壁際に立っている片桐さんとアイコンタクトを交わす。片桐さんはいつものように、人好きのする微笑みを浮かべた。
四階で僕たちは示し合わせたように降りる。喫煙所に向かうのが僕たちの日課だった。
「おはよーう」
片桐さんが、間延びした声で言った。
喫煙所へ向かうと、入れ違いに井田と人事部の宮原 悦子が出てきた。二人とも、今夜のプレゼン会議のメンバーで、彼らはプレゼンする方ではなく、される方──つまり僕らの説明を聞く側だ。瞬間的に緊張が走り、「お、おはよう」と声をかけたが、井田は静かに目を伏せただけだった。宮原もおどおどとした様子で、軽く会釈をして去って行ってしまう。
人事部所属。仕事の処理能力は高いが、本人のモチベーションは低い。おとなしい性格ゆえ、頼まれると断ることができない。
「宮原さんも煙草とか吸うんだねえ」
片桐さんがいかにも意外、というようにそう呟いた。片桐さんも、プレゼン会議の「説明を聞く側」のメンバーの一人だった。
喫煙所の自販機の横に陣取ると、僕たちはしばらく言葉も交わさず、ゆっくりと煙草を吸い続けた。黄ばんだ天井を煙が昇り、蛍光灯の周りには虫が飛んでいる。
「あれ? こんなとこにヒビなんて入ってたっけ?」
片桐さんが、寄りかかっていた柱の右ひじの辺りを見ながら言った。そんなことはどうでもいいじゃないか、とは思いつつ「どうでしたかねえ」と気のない返事をした。
「きっと、誰かが肘でもぶつけたんだな」
前から気になってたんだよこの柱、前に出すぎじゃない? と片桐さんが言う間、少しだけ純の顔が頭を過ぎった。
「煙草、前々から彼女に『やめてくれ』って言われてるんですよ」
僕は言った。
「ありゃ、それは拷問だ」
片桐さんがふふ、と笑った。
「そういう時って、『いいよ』って言えばいいんでしょうかね。でもさすがに、嘘は良くないかなって」
「うん、嘘は良くないね」
「なんか、最近彼女とはそんなやりとりの繰り返しで」
話しながら、「自分は純のことを誰かに話したかったんだ」と、僕は気づいた。片桐さんはうんうんと頷きながら、「わかるよ」と言った。
「だけどね、親しければ親しいほど、そういう気苦労は多くなっていくんだなこれが。俺も一回、禁煙したことがあるんだけどね」
「はい」
「ある日、奥さんが旅行に行きたいって言ってパンフレットを渡してきたのよ、海辺の綺麗な表紙の。で、その何ページ目かに夕日をバックにした灯台の写真があったんだけど、俺それが火のついたタバコに見えちゃったんだよね。もう限界だと思って、禁煙は諦めた」
「はあ」
「俺からの教訓が一つ」
片桐さんが再びヒビを指さした。
「我慢ばっかりしてると、ヒビが入る!」
「何ですかそれ」
思わず僕は吹き出してしまう。勢いよく吐き出した煙が目に染みて痛かった。
「よし、そろそろ時間だよ、戻ろう」
片桐さんに肩を叩かれた。片桐さんなりに気を紛らわせようとしてくれたのかもしれない。少しだけ胸が軽くなった気がした。
5
「もうすぐ21時ですが、このまま続けますか?」
ファシリテータ役の宮原が、会議中はじめてそう発言した。プレゼン会議が開始されて、2時間が経とうとしていた。
僕は彼女の方を向いて何か応えようとしたが、うまく言葉が出てこなかった。彼女は僕と一瞬目を遭わせたあと、すぐにノートPCに目線を戻してタイピングを続けた。
会議の進行役。株式会社ワークカラットでは、1時間を超える会議を行う際はファシリテータを付けることが義務付けられている。また、会議のファシリテータは人事部の人員が担われるのが通例となっている。
だが、制度としてはやや形骸化しており、実際に会議に参加するファシリテータは議事録の作成程度にとどまっていることが多い。
僕と宮原以外の参加メンバー、伊藤、田中、井田、片桐さん、皆が無言だった。この会議をどう終わらせるべきか、皆見当がつかなかったのかもしれない。ただ、新企画プロジェクトのプレゼンが失敗に終わりつつあるということは、誰の目にも明らかだった。
なんでこうなってしまったんだろう──、混乱する頭で僕は必死に考えた。出だしは好調だった。伊藤が今回のプレゼンの主旨であるWebメディア企画を話し終えたとき、決裁委任役の片桐さんも井田もそれなりに身を乗り出していたように見えた。
ただ、その後の田中の説明があまり良くなかった。ターゲットユーザーへの訴求ポイントをたどたどしく話した後、運用プランについてはいくつか説明すべき箇所を飛ばしてしまい、そのたびに前後の繋がりが途切れ、聴いていた井田と片桐さんは何度も「ん?」という表情をした。──そこで僕がフォローに入っていれば、もしかしたら結果は変わったのかもしれない。でも、田中の面目もあるだろうと思い、「自分が代わりに説明してしまいたい」という気持ちをぐっとこらえ続けた。
田中は続いて、今回の企画のベンチマークにしていた他社の類似サービスの説明と、いかにそのサービスが優れているか、そしてその優れた点を上手に取り入れれば今回の新プロジェクトもうまく行くだろうということを伝えた。その内容は、僕が何度か伊藤と田中に話していたことだったが、プレゼンで伝えることは想定していなかった。
「すでに他社で同じことやってるサービスがあるんだったら、二番煎じになるんじゃないの?」
案の定、井田がそう指摘してきた。
「いや、まったく真似するわけじゃなくて、良いところを取り入れようってことだから。今回の企画の一番のウリは、そこじゃなくて」
僕は急いで井田にそう言ったが、彼は僕を一瞥しただけで何も答えず、眉間にしわを寄せながら手元の企画書に目を移した。
「なるほど、なんか既視感あるなぁと思ってたけど、あのサービスか。確かに、似てるね。これ」
味方になってくれると思っていた片桐さんも、企画書をパラパラとめくりながらそう呟いた。──いつの間にか、会議室に重苦しい空気が流れていた。なんとか流れを変えなくてはと、僕は(この状況からは、自分が説明役を担うべきだろう)と決めて、プロジェクトの要点を更に詳しく説明した。サービスの独自性から、収益への期待、現存サービスとのシナジー効果等──ときに自社の失敗事例や成功体験を織り交ぜながら、そして、井田と片桐さんの様子を窺いながら。
説明を続けていくうちに、僕はだんだんと喉の奥がつかえるような息苦しさを感じはじめていた。井田も片桐さんも、僕の話に相槌を打ちながらも別の視点で考察をし始めているのが見て取れた。僕の隣に座る伊藤と田中の表情が段々と暗くなっていくのが、視界の外から伝わってきた。
「あのさ、今うちの事業部の業績がどんどん落ち込んできているのは、知ってるよね」
僕の説明がひと段落ついたタイミングで、井田が急に優しい口調になってそう言った。──僕にではなく、伊藤と田中に向けて話しかけていた。
「その理由は、既存のサービスの売上が落ちてきているからだよね。でも、だからと言ってそれらサービスを止めてしまうわけにはいかない。なぜなら、それらに代わって売上を出していける新しいサービスがまだないからね。そうしたら、収益は完全にマイナスになる。
だから、みんな自分たちが運用するサービスがもう時代遅れで、そして衰退期にあることも自覚したうえで、その衰退の進行が少しでも緩やかになるように、歯を食いしばって取り組んでるわけだよね」
井田の淀みない説明が、この場をすこしずつ支配していくように感じられた。
「この新プロジェクトは、そんな閉塞感を打破していけるような、事業部の皆が希望を持てるようなものにしていく必要があると思うんだ。じゃないと、今既存サービスに必死に向き合っているメンバーに申し訳が立たないんじゃないかって。──君たちは、それくらいの想いと覚悟を持って、このプロジェクトに向き合えているのかな」
片桐さんが、井田に同調するように何度か大きく頷いてみせた。伊藤と田中は、井田の問いかけに答えられずにいた。僕も、そうだった。数分の沈黙が、──宮原が21時の通報を発するまで、続いた。
「横井クーン」
プレゼン会議が終わり、片桐さんがいつもの人懐っこそうな声に戻って声をかけてきた。いつの間にか、部屋は僕と片桐さんの二人だけになっていた。
少し前に宮原から、会議終了のアナウンスと共に、今後については明日井田と片桐さんが今回のプレゼン内容と所感を部長に報告し、その後部長からプレゼン通過可否を通達すること、そしてその通達は2日後になることを説明された。僕は宮原の説明を聴きながらも、ここからどうやったら挽回できるかを必死に考えていた。会議中に企画書の端にメモ書きした内容を見ながら、あるかどうかも分からない「次の打ち手」を探して続けていた。
呼びかけた声の方を見やると、少しだけ優しそうに目を細めた片桐さんが、そこに立っていた。
「あれは、良くなかったんじゃないかな」
片桐さんは、少しだけ優しい表情のまま、僕にそう言った。
「すみません、もうちょっとしっかりプレゼンの準備をしておくべきでした。後で少し相談させて──」
「いや、そうじゃなくてね」
片桐さんは僕の言葉を遮って、話を続けた。
「プレゼンのことじゃなくて、その後の、伊藤さんと田中くんに対してだよ」
「え?」
「ふたりとも、会議終わった後に心配そうに──というか、不安そうに、かな。ずっと横井くんのこと見ていたよ。だって、横井くんずっと頭抱えちゃって下向いたままだったから」
「あ……、そうだったんですか」
「ふたりのこと、全然気づかなかった?」
「──はい」
「そりゃ、良くないよ」
片桐さんはもう一度、そう言った。
「プレゼンがうまく行かなくて、一番苦しんでるのは、間違いなく君だろうけどさ。でも、そこでマネージャーはまず、部下のことを気遣ってあげなきゃ」
僕は急いでデスクに戻った。──そうだった。伊藤も田中もこの日のプレゼンの為に、毎日遅くまで残業して頑張ってきたのだ。彼女たちをきちんと労ってやらなければ。そして、これからまた気を取り直して頑張っていこうと、伝えておかないと。二人とも、デスクで僕のことを待っているかもしれない。会議室を出るときに、片桐さんが「これから大変だろうけど、めげずに頑張ってね」と励ましてくれた。
デスクに戻ったとき、何人かの社員はまだ残っていた。僕は伊藤と田中の姿を探した。でも、どこにもいなかった。二人の机がきれいに片付けられているのを見て、伊藤も田中も、会議室から戻ってからすぐに帰ったんだということを、僕は知った。
6
たった一駅ではあるが、足取りは重く、気分も沈みがちだった僕は、電車で帰路についた。先ほどの企画会議の熱がいまだに全身に籠っているようで、Yシャツは汗で背中に貼りついたままだった。
携帯を見ると、三時間ほど前に純からメッセージが届いていた。
『まだ帰って来れなそう?』
昨晩の純との会話を思い出す。そうだ、純は何か話があるのだと言っていた。それに対して僕は「会議があるけど、そんなに長くはかからないんじゃないかな」とよく考えもせず返したのだった。
少なくともあの時は、企画会議は滞りもなく進むのではないかと慢心していた。直前に準備に根を詰め過ぎても不安が増すだけだと思っていたが、実際には「準備」のスタートラインにすら立てていなかった。
自分の根拠のない楽観主義と、先ほど片桐さんからかけられた言葉によって、途端に自己嫌悪の気持ちがせりあがってきた。あげくに純との約束すら守れず、僕は誰に対しても誠実ではなかった。
玄関の扉は昨日に引き続き鍵がかかっていなかった。夜気に触れて冷たくなったドアノブを握りしめ、いつもより数段重く感じる扉を開けた。扉の向こうで笑顔の純が待っている、そんな淡い空想を抱いていた。
「ただいま」
「おかえり」
奥のリビングから、くぐもった彼女の声が聞こえた。僕は二日酔いの時のような胃の重みを感じていた。
「ごめん、会議が長引いちゃってさ」
努めて明るい声でリビングのドアを開けると、昨夜と同じ位置で、彼女がソファに座ってテレビを見つめていた。昨日と違うのは、テレビの電源は消されたままであることだ。
「話って何? すぐ終わりそうもない話なら、先に何か食べてもいいかな? 腹減っちゃってさ」
「……事前に連絡できる時間くらいあったでしょ?」
純が、ひどく緩慢な動作で僕の方を向いた。化粧を落とした後の顔は、いつも幼い印象を僕に与えるが、今日は違った。彼女の視線の先は僕の顔というより、二人の間の何もない空間へ向けられているような気がした。
「本当にごめん。ここまで長引くのは本当に想定外でさ……。ほら、前に言った新企画の話。その会議が今日だったからさ、あまり他の事とか考える余裕なくて」
「うん、それは分かるよ。でもさ、もし少しでも私との約束を覚えていてくれたんなら、どこかのタイミングでたった一言、今日は遅くなるかもって伝えてくれるだけで全然印象は違うでしょ?」
彼女は相変わらず視線を中空に漂わせたまま、それでもどうにか口元に笑みを浮かべようとしている。けれどそれはひどくぎこちない微笑みで、一層罪悪感がこみ上げてきた。
「もし、今からでも間に合うんなら、この後いつまででも話を聞いてあげられるよ」
慎重に言葉を紡ぐ。これまでささやかな言い争いは何度もあったが、今日のような空気はまだ味わったことがなかった。
「……だって、あるんだよ?」
「え?」
「間に合わないことだってあるんだよ?」
初めて、純と正面から目が合った。彼女の目元には涙が溜まっており、僕は戸惑いを隠せなかった。
.gif)
「カズも私も、今は仕事の忙しさに揉まれて、お互いのことが思いやれていないと思うの。今日だってそうでしょ? カズが忙しくしてるのなんて、私だって充分分かってるよ。それでも、私との約束を守らないのはまた別の話だと思わない?」
「そりゃそうだけど……」
僕は言い淀んだ。企画会議における僕の情熱は、以前から何度も彼女に説いてきたはずだ。それに対する労を、少しは労ってくれてもいいんじゃないか、そんな不満も湧き上がってくる。
「今だってカズはどうせ、昨日今日、私が急に機嫌が悪くなったくらいにしか思っていないんだろうけど」
純がブラウスの袖口で乱雑に目元を拭った。
「そんなんで、私たちこの先うまくいくと思う?」
目元を拭う手を止め、純は静かにうずくまった。
うずくまる純を、僕はしばらくの間見つめていた。
何かを言わなければならないとは思ったが、同時に「何で今日は、こんな目にばかり遭うのだろう」と思っている自分もいた。純の言葉を思い返すほど、今日の仕事での一連のシーンも、頭の中を巡っていく。
「俺はちゃんと考えたいと思ってるし、毎日考えてるよ、純とのこれからのこと。仕事で忙しい時でも、何となくだけど、純がそばにいてくれてる気がするんだ。だから、俺はもっと頑張らなくちゃって思えるんだ。俺にとって、純はそういう存在だよ」
うずくまる純の小さな背中に手を置いた。彼女のやはり規則的なリズムの呼吸が伝わってくる。
純はゆっくりと顔を上げると、赤くなった目元で、僕の顔をじっと見据えた。
「……何それ」
純は僕の手をゆっくりと払うと、そのまま何も言わずに寝室へ引っ込んだ。しばらく待ってみたが、彼女が戻ってくる気配はない。
彼女のしたかった話は、多分こんなことじゃなかったはずだ。そうは思ったものの、溜め込んでいた一日の疲れがどっと押し寄せ、「とにかく今は眠りたい」と僕は思った。
彼女と同じベッドに寝るのは気まずく感じられ、その夜はリビングのソファーに横になった。
この一日が終われば、明日はもう少しマシな一日になるのではないか。ほとんど祈るような気持ちで僕は考え、その思考も、押し寄せる眠りの波にたちまち呑まれていった。
朝になって目が覚めたとき、純はもういなかった。
[続く]
<スポンサーリンク>

