「労基法って何?」管理職・マネージャーが押さえておきたい労働基準法(基本編)
[最終更新日]2019/07/26
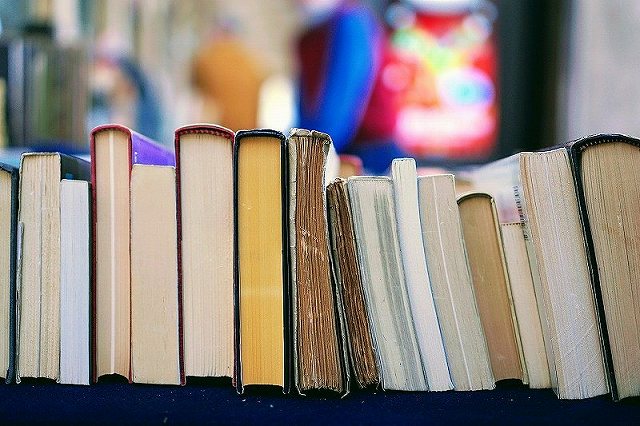
労働基準法とは、どういうものかきちんと理解できていますか?
2018年、改正案が新たに可決されました。
こちらの記事では、この「労働基準法」にスポットを当てて、基本事項を解説していきたいと思います。
具体的には、法定労働時間、36(サブロク)協定、フレックスタイム制、法定休日や休憩、振替休日・代休、年次有給休暇などについて取り上げてみたいと思います。
いずれも、管理職やマネージャーとして押さえておきたい項目になります。新しく改正される内容も含めて、しっかり理解していきましょう。
Index
目次
<スポンサーリンク>
そもそも、「労働基準法」とはどんなもの?労基法の起源・由来は?

労基法(労働基準法)とは
労働基準法とは、賃金、労働時間、休暇などの条件の最低基準を定めた法律です。
有給休暇日数、就業規則、雇用形態に関する規定、解雇などの内容も含まれます。労働者の保護や、労使双方の立場を公平に保つため、昭和22年(1947年)に制定されました。
定められた基準を下回る条件での労働契約は無効です。
つまり労働基準法で定められていることは、無条件に労働者に与えられた権利とも言うことが出来るのではないでしょうか。
基準を下回る条件で労働させれば、法律違反で罰せられるのです。発覚した場合は、企業に対する罰則規定も設けられています。
労基法(労働基準法)の歴史
労働基準法が制定されたのは、戦後になります。軍国主義だった日本を民主化にシフトするため、GHQが政策の一環として規定要求をしたのです。
戦前の日本は、製造業を中心に著しい経済発展を遂げていました。しかし、その背景には、国内外において低賃金労働などの劣悪な雇用環境があったと言われています。
軍事(戦争)への発展性の否めない状況でもあったため、GHQがメスを入れたというわけですよね。
その後、労働基準法は、経済情勢やビジネス環境の変化に応じて、数々の改正が行われてきました。
週40時間労働制は、昭和62年(1987年)に導入、平成3年(1993年)に原則化されました。
長時間労働の抑制は、平成10年(1998年)に始まっています。
2000年以降は、雇用形態の多様化に伴う改正、時間外労働に対する賃金設定、休暇日数や休暇取得に関する詳細の法改正などが、目立ってきています。
2015年には、長時間労働に関する内容が厳しくする改正案が出されました。
裁量労働制、高度プロフェッショナル制度、長時間労働是正のための改正案も加わり、審議が重ねられました。
この改正案は2018年6月に可決され、2019年より順次施行される運びとなっています。
労基法の基本(1) 法定労働時間と36(サブロク)協定

労働基準法の基本中の基本項目として、法定労働時間と36(サブロク)協定がまずは挙げられます。
管理職やマネージャーとして、部下の勤怠管理と関わりの深い項目というのは周知のとおりですよね。2018年の可決法案でも大きな変化もあったので、早速チェックしておきましょう。
法定労働時間とは
法定労働時間とは、文字通り、法で定められた労働時間の限度です。この法が労働基準法(第32条)となります。
法定労働時間には、2つの原則があります。
- 一週間に40時間以上勤務させてはならない
- 一日あたり8時間以上勤務させてはならない
この労働時間の中には、休憩時間は含まれません。
注意しておきたいのが、所定労働時間との違いです。所定労働時間とは、企業と労働者の間で取り決める契約上の労働時間を指しています。
昨今は、週40時間で一日8時間のフルタイムの正社員ばかりでなくなっていますよね。週の出勤日数や一日あたりの労働時間を選択して働ける企業も増えています。
たとえば、週3日、一日4時間という契約で働く従業員の労働時間は、一週間で12時間という計算になります。
「一日4時間」「一週間で12時間」、これらが所定労働時間となります。
この所定労働時間は、労使間で同意のもとに自由に決めることができます。ただし、法定労働時間の範囲内としなければならないというのが原則的なルールとなっているのです。
36(サブロク)協定とは
さまざまな事業がある中、週40時間でカバーしきれていないのが日本のビジネス環境の現実です。さらに国内外でビジネス競争も激化や人手不足の深刻化が、そこに拍車をかけているのが現状です。
これでは、法定労働時間に違反する企業ばかりになってしまうと言わざるを得ません。
そこで制定されているのが36(サブロク)協定です。
36(サブロク)協定とは、法定労働時間の範囲を超えた労働(残業、休日出勤など)があることを、企業と従業員で同意(協定締結)することです。その締結を、事業所管轄の労働基準監督署に届け出ることで、労働時間に関する基準やルールの枠を広げることができます。
36協定における残業の上限の原則
- 一か月45時間
- 年間360時間が原則
特例的な事情が認められる事業での上限(大企業:2019年4月~、中小企業:2020年4月~)
- 一か月100時間未満(2~6か月平均80時間)
- 年720時間(月平均60時間)
1988年から導入されたフレックスタイム制について
フレックスタイム制度とは、一定期間(清算期間)において所定労働時間をカバーしていれば、従業員が、始業と終業時間を自由に設定できるというものです。
この制度では、企業側が勤務すべき時間帯(コアタイム)を指定していることも多いというのが一つの特色です。
従来の制度では、その清算期間は最長で1か月とされていました。
2018年の法案可決により、最長3か月まで設定できるようになります。(2019年4月より)
子育て世代の労働者が、仕事と子供の長期休暇やイベントとの調整を図れることも狙いのひとつと言えるでしょう。
一方で、フレックスタイム制での労働時間の計算は、やや複雑になるため注意が必要です。従業員の利用状況を確認したうえで、勤怠管理をしっかりと行っていきましょう。
労基法の基本(2) 法定休日、休憩、振替休日/代休について

次に、労働基準法に定められた法定休日、休憩、振替休日や代休についてご紹介していきましょう。
働く従業員にとっては何よりもまず重要な項目になっていますので、管理職やマネージャーなど、従業員を管理する立場の方にとっては、ぜひ押さえておきたい項目になります。
法定休日
労働基準法(第35条)における法定休日とは、従業員に与えなければならない休日のことを指します。
企業は、一週間のうち、最低一回は休日を与えなければならないと定められています。四週間のうちに4日間でも構いません。この日数の計算は、午前0時から午後12時の継続した24時間でなければなりません。
休日については、所定休日という括りもあります。
たとえば、週休2日の場合、法定休日以外の休日が所定休日です。法定休日と所定休日では割増賃金率が異なるので注意が必要です。
法定休日の労働では、休日割増賃金=35%以上、深夜割増賃金=25%以上です。
所定休日の労働では、時間外割増賃金=25%以上、深夜割増賃金=25%以上です。
時間外労働が月60時間を超える場合は、大企業では割増賃金率が50%となります。2018年の改正案可決により、中小企業も従来の25%から50%への移行が必要になる点は特に注視したいポイントでしょう。
いずれも36協定の締結と届出が必要です。
休憩
労働基準法の第34条では、労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分の休憩を与えると定められています。8時間を超える労働の場合は、1時間以上の休憩が必要です。
また、19条の中で、休憩について下記のような規定があります。
- 休憩時間は、労働者に自由に利用させなければならない
念のための待機など、完全に労働から離れられないような時間は休憩ではありません。 休憩場所の限定など制限がある場合も、「労働からの解放」は、確保する必要があります。
- 休憩時間は、事業場すべての労働者に一斉に与えなければならない
交代で休憩を取ることをルールにする場合は、事前の労使協定が必要です。
振替休日/代休
振替休日と代休の違いについて、頭では理解できていても、実際に説明するとなると難しいという方もいるのではないでしょうか。
いずれの規程も就業規則に定められていなければならない、社員にとっては大変重要な項目です。
振替休日
振替休日は、所定の労働日と休日を入れ替えることであり、休日出勤にはなりません。従って、割増賃金も発生しないことになります。振替休日の指定には、以下のような原則があります。
- 前日までに通知する
- 取得前に振り替える日を特定する
- できるだけ近接日にする(四週間4日間を保てるよう)
なお、その振替日に勤務になった場合、休日出勤の扱いとなります。
代休
代休は、振替休日の手続きが取られていない場合の休日となります。イメージとしては、後付けの休日ということになるでしょう。
この場合の労働日は休日出勤の扱いとなり、割増賃金が発生します。
後で休日を与えるからといって帳消しにはなりません。
また、振替でも代休でも、働く日を含む週の労働が40時間を超える場合は割増賃金が発生します。
労基法の基本(3) 年次有給休暇について

2018年に可決された法案には、年次有給休暇についての変更も盛り込まれています。従業員のワークライフバランスを支援する側としても、理解と実践が必要になってきます。
自ら積極的に取得し取得を促せる管理職、マネージャーを目指しましょう。
年次有給休暇の概要
年次有給休暇については、第39条に定められています。
- 6か月勤続勤務
- その期間の出勤率が8割以上
上記の2つの要件を満たす従業員は、自動的に年次有給休暇が取得できます。正社員、パートなどの雇用形態に関わらず、全員が対象となる点を知っておきましょう。
付与される年次有給休暇の日数は、労働日数や勤務時間によって異なります。
たとえば、週30時間以上勤務する従業員の場合は、10日以上が付与されます。一年半後からは、1~2日ずつ加算され、勤続6年半以上は20日以上と定められています。
対して週30時間未満の従業員は、労働日数や勤務時間に応じて日数が定められています。
この場合も、勤続年数が増えるごとに日数は加算されます。
有給休暇の取得有効期限は、2年間です。つまり、その年に残った日数は、翌年まで繰り越されます。
年次有給休暇のルール

年次有給休暇は、従業員が自由にとれる休暇のはずなのですが、企業の風土や慣行などもあって、なかなか取らない、取りにくいという現状が続いています。読者の皆様も、一度や二度はそのような経験をされたことがあるのではないでしょうか。
2018年の可決法案では、10日以上の有給が付与される従業員に対して、うち5日間については、企業側が取得日を指定することが義務化されます(大企業:2019年4月より、中小企業:2020年4月より)。つまり、少なくとも5日間の有給を確実に取得する人を増やすための規定であり管理が必要になるのです。
いくつかの方法で取得を促すことができます。
- 企業内で一斉に休暇日を設ける
- 部署や事業所内において交代で取得する
- 個人で取得計画を提出させる
年次有給休暇は、通常1日単位の取得ですが、従業員の希望があれば半日単位での取得も認められます。また、時間単位での取得も可能ですが、労使協定の締結が必要となります。
年次有給休暇の注意点
最後に、年次有給休暇の取得推進について下記の通り、いくつかの注意点をご紹介します。いずれも管理職・マネージャーの立場の方にとっては、部下の効率的な業務遂行に際して必要不可欠のことですので、下記を参考に風通しの良い、働きやすい職場を目指してください。
・取得に理由を求めない
有給休暇の取得目的を制限してはいけません。有給休暇は、理由がなくても取得できる休暇です。
・要件に満たない従業員でも、企業の一斉取得日には有給対象
企業で一斉に有給休暇取得日を設定し休日とする場合、入社から半年に満たない社員がいることもあります。この場合も、有給対象となりますので、取得をためらわせるような言動は慎むようにしましょう。
・買取は可能か
従業員からの希望があった場合は、買取は可能です。
・休業中の有給消化
出産、育児、介護などの休業時でも、従業員が希望すれば有給取得は可能です。
ただし、その休業ごとに申請する助成金や補助金などに申請している場合は注意が必要です。それらを受給するには、給与が支払われていないことが要件となっているものもあります。企業の担当者や従業員としっかりと確認されることをおすすめします。
まとめ 労基法を理解して部下の労働環境をバックアップ

労働基準法は、すべての労働者を守るために制定された法律です。
一人のビジネスパーソンとして、充実した働き方をするために知っておくことが何よりも大切になってきます。
そして、管理職・マネージャーとして、部下や組織の働き方への配慮も欠かせない要素となります。
人手不足が深刻化する中、メンバーの残業を削減することにも気を配る必要があります。
一人ひとりの働き方や仕事のスタイルを尊重できるよう、まずは、労働基準法で定められていることをよく理解しておくことが大切です。
この先も、改正が重ねられると思います。
ビジネスパーソンの共通認識項目の一つとして、常にキャッチアップしていきましょう。
<スポンサーリンク>

